
あなたは今、誰かを支えていますか?
人は誰でも、どんなときでも、誰かに支えられ、支えながら生きているもの。私も、あなたもそれはきっと同じです。
そして、人は心身の不調や、年を重ねることで、いつもよりさらに大きな支えやケアが必要になることもあります。
肉体的、精神的な痛みや苦痛を抱えることは、とても辛いこと。そんなとき、寄り添ってくれる誰かの存在や温かな手に救われたという経験を持つ人はたくさんいるでしょう。
2年前に亡くなった私の祖母は、認知症になっても最期まで家で生活をしていました。祖母に会いにたまにやってくる親戚たちは「おばあちゃん、顔色も良くて元気そうで良かったわね!」と言って祖母の手を握っていました。
それはごく自然な温かな光景に間違いありません。ただ、おばあちゃんがそこにいるためには、毎日欠くことができない、たくさんのケアが必要だったのです。
でも、もし、身近な人を「元気になってほしい」という気持ちで支えつづけても、よい方向に向かうことがなかったら。手助けが必要なことの方が増えていったら…。
ケアを必要とする人に思いを馳せることはあっても、その近くでケアしている人の思いは、ついつい忘れがちになってしまっているかもしれません。
しかし、「ケアしている人へのケア」は、苦痛や困難を抱える人へのケアと同様に、必要なものではないでしょうか。
その問いの答えがほしくて、私たちは東京小金井市で家族介護者をサポートしているNPO法人UPTREE(以下UPTREE)の代表である阿久津美栄子さんに会いに行ってきました。
“ケアする人をケアする場所が必要”という思いから


瀬戸は日暮れて〜夕波小波〜♪ あなたの島へお嫁にゆくの〜♪
若いと誰もが心配するけれど〜♪ 愛があるから大丈夫なの〜♪
私たちがこの日訪れたのは、とあるカフェの2階。「認知症カフェ おれんじ」(以下、おれんじ)の開催場所です。
扉を開けて、まず耳に飛び込んできたのが「瀬戸の花嫁」の大合唱。アカペラですが、みんながニコニコと楽しそうにしている様子が伝わってきます。
認知症の家族を介護している人、認知症当事者、これから先、自分自身や家族が認知症になるのではと心配している人など、さまざまな方が参加するおれんじ。
それぞれが、おしゃべりをしたり、工作をしたり、お昼ご飯を食べたり、歌をうたったりと充実した時間を過ごしているようでした。
このおれんじを主催しているのがUPTREEです。当事者はもちろん、認知症の家族を介護している人などが集まり、同じ思いを共有することでそれぞれの居場所をつくることを目的としています。
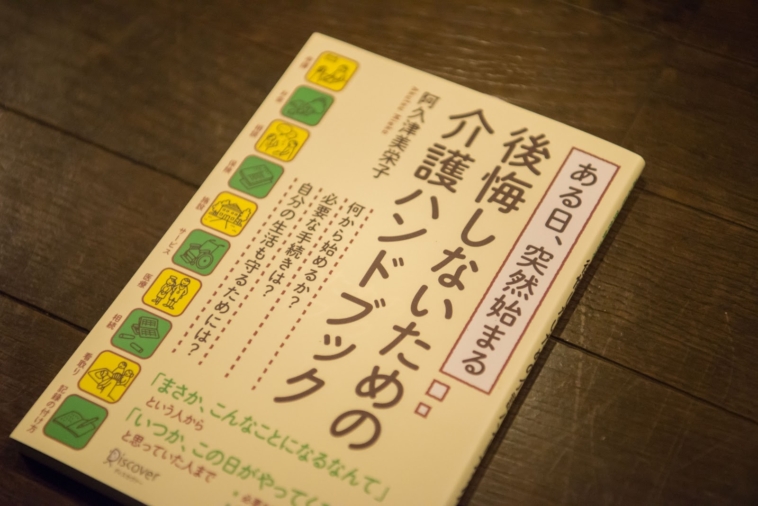
“ケアする人をケアする場所が必要”そんな思いでUPTREEを立ち上げたのが代表の阿久津さんです。自身も両親の介護を経験し、後にその経験を基に、「ある日突然始まる 後悔しないための介護ハンドブック」という本を出版されています。
介護をしているときは、孤独だった。
そう話す阿久津さん。ご自身の体験や思い、介護のなかから得たもの、そして、UPTREE立ち上げから現在に至るまでのお話を伺いました。
ある日突然、一本の電話から始まった母の介護

母さんが、倒れた。
ある日突然、阿久津さんの元にお兄さんから一本の電話がかかってきました。当時37歳だった阿久津さんは、夫の転勤で大阪に在住。お子さんにも恵まれ、順風満帆な生活を送っていたといいます。
4歳だった娘さんがかわいくて、娘さん中心の生活に幸せを感じながらも、「このままでは娘に依存してしまう」と、パソコンインストラクターのパートを始めたばかり。
お兄さんからの電話を受け、実家がある長野に戻った阿久津さんは、そこで、お母さんが肺がんで、脳に転移があること、余命は3ヶ月ほどだということを医師から宣告されました。
阿久津さん:医師に宣告された瞬間は、受容ができなかったんです。でも、余命3ヶ月ってことは、もうすぐ死んでしまうってことだよね…。そんなふうにじわじわ理解が進むにつれて、さーっと血の気が引いていきました。
お母さんは、まだ70代。祖父母が全員90代で亡くなっているので、もっと長生きしてくれるのだと思っていた。余命宣告されてもなお、阿久津さんは現実が信じられずにいたのです。
思い描いていた未来が、がらがらと崩れたと阿久津さんはうつむきます。
阿久津さん:それでも、「余命3ヶ月」という宣告があったから、「よしやろう」と心に決めることができました。たとえば、先が見えない状況だったとしたら、この段階でそう決められたかは、分かりません。
それから、月に1度、一週間から10日ほど、大阪から長野に帰る生活が始まりました。基本的には、娘さんも一緒に。緊急のときは、娘さんを旦那さんにお願いして阿久津さん一人で長野に向かったこともあったそうです。
それに加えて、娘さんが通う幼稚園が夏休みなどの長期休暇のときには、その間ずっと実家で過ごす生活が続いたのです。
実家にはお父さんがいて、近くにはお兄さんも住んでいました。でもが、お兄さんはなかなか“死と向き合う”ことができず、介護については阿久津さんに任せきりだったといいます。
「余命3ヶ月」そう宣告されていましたが、その3ヶ月はあっというまに過ぎ、1年、2年と時間が流れていきました。
「誰も分かってくれない。」孤独と戦う毎日

大阪と長野を行き来しながら、お母さんの介護をする生活は、時間が経てば経つほど、肉体的にも精神的にも、阿久津さんを追い込んでいきました。
介護と育児、ふたつを同時に担っていた阿久津さん。娘さんがどんどん言葉を覚え、成長していく一方で、お母さんは、言葉を失い、おむつをつけ、寝たきりになっていく…。
おむつを外したばかりの娘さんがお漏らしをしてしまい、お母さんはおむつを汚してしまう。そんなことが同時に起こる毎日の中で、どこにもぶつけようのない気持ちが阿久津さんの中に溢れてきました。
阿久津さん:「なんでこうなの?なんで私の母親がこうなるの?」っていう思いでいっぱいでした。それもすべてに罪悪感を持つようになりました。大阪の自分の家や家族のことが満足いくようにできなかったんです。そして、母の介護も完璧にできていない。何もかもが中途半端なのが、しんどかったです。
特に4歳の娘さんのことは、これからどうなってしまうのだろう、という不安が強かったといいます。習い事も休ませ、長期休暇のときには、お友達もいない長野でひとりぼっちで過ごさせてしまっている。それが何より一番大きい罪悪感でした。
阿久津さんの脳裏に焼き付いているのが、まだ小さかった娘さんが実家のテレビの前で、ぽつんとアニメを見ている姿。その光景を思い出す阿久津さんの目には、じんわりと涙が浮かんでいました。
阿久津さん:その時期に友達と呼べたのは、娘を介して仲良くなった、いわば“ママ友”でした。その中に介護を経験した人はいません。介護のしんどさを話したときに「精神科に行けば?」と言われたことがとてもショックで…。もう他人には介護の話はしないと完全に自分でシャッターをおろしてしまいました。そこから、さらに孤独との戦いが始まったんです。
居場所もなく、サポートもない。そんな中で、徐々に阿久津さん自身も体調の悪さを感じるように。「自分自身をケアしなければ」という思いで、月に一度はアロママッサージに通おうと決めました。
阿久津さん:でも後になって気づいたんですが、マッサージを受けているときも全く休めていなかったんです。頭の中は、母や家のことでいっぱい。唯一、すべてを忘れて目の前のことに没頭できたのは、仕事をしているときだけでした。
パソコンインストラクターとして働いている時間は、エクセルで関数を使ったりとしっかりと計算ができていました。ただひとたび仕事から離れると、お釣りの計算もできないくらい、頭が回らないこともあったのだとか。精神科に行くことを勧められたことにショックを受けたけれど、本当はうつのような症状だったのかもしれない、と阿久津さんは振り返ります。
余命宣告を受けていた阿久津さんのお母さんは、いつ何があってもおかしくないという状況。大阪の自分の家にいても、気になって仕方がなかったといいます。
阿久津さん:「急変した」という電話が今にもかかってくるんじゃないかと思うと怖くて怖くてたまらなかったんです。針のむしろにいるような状態が何年も続きました。
母に続いて父が。二人の介護を担うことに

余命3ヶ月、そう宣告されて始まった介護生活が4年目に差し掛かる頃、予想もしていなかったことが起こります。
阿久津さん:母に続いて、父が倒れたんです。父は母が倒れる以前に、直腸癌で手術を受けましたが、根治していたはずでした。それが再発した、と…。
再発したことをお父さんはしばらく黙っていたといいます。当時を思い返すと、とても言える状況ではなかった、と阿久津さんは話します。
阿久津さん:父の場合は、余命宣告はありませんでしたが、なぜ私たち家族だけが、こんな目にあうのだろう。神も仏もないというのはこのことだと思いました。もう、周りの人たちがみんな敵に見えるんです。娘ですらも。
もちろん、娘さんをはじめ、周りの人が阿久津さんを直接脅かしていたわけではありません。「誰にも理解されない」という気持ちから、自分ですべてを排除してしまい、誰もが敵のように見えていたと阿久津さんは振り返ります。
「自分だけですべてを抱え込んでしまう」それは、介護をしている人の多くが陥りがちなことだといいます。
阿久津さん:最近、ニュースなどで目にする、“介護している人”が“介護されている人”を傷つけてしまうような事件も、“介護している人”が抱え込んでしまうことで、起きてしまっているように思います。責任感から、子どもや家族に迷惑をかけられない、と自分で自分を孤独にしてしまうんです。その結果、配偶者や親など家族を手にかけてしまう人もいます。
お母さんとお父さんの入院先は別々の病院だったこともあり、阿久津さんはさらにハードな生活を送ることになりました。
また、当時お母さんが入院していたのが「急性期病棟」。急性期病棟とは、刻一刻と変化し、予断を許さない病状に対応してくれる病床のこと。ただ、入院期間は3ヶ月までと決まっていたので、3ヶ月後の転院先を常に探しておかなければいけませんでした。
そんな中で、良い出会いも巡ってきます。お父さんの主治医だった医師は、介護をしている阿久津さんに寄り添ってくれる先生でした。
阿久津さん:お父さんのことは最期まで診てあげるよ、と言ってくださって。介護生活の中では、すごく落ち着いた時間でしたね。でも、結果的には両親とも最期はホスピスで迎えました。
疲弊した阿久津さんは、最終的に両親ともに同じホスピスに入れるという選択をしたそうです。
両親との別れ、喪失感に襲われながらも、グリーフケアに出会う

阿久津さん:父は、母より自分が先に逝くなんてことを考えていなかったと思うんです。母の面倒をみる、という気持ちから、副作用の出る薬は飲まず、治療は拒否していました。
でも、お父さんは、倒れてから4ヶ月という短い時間で亡くなってしまいます。その2ヶ月後にお母さんが亡くなり、阿久津さんは短いあいだに両親を失いました。
阿久津さん:ものすごい喪失感に襲われました。何もする気にならないし、介護中に周りが敵に見えたと話しましたが、それがより一層強くなった感じもしました。でもそのときに、「どうして人は死ぬんだろう」ということを考え始めて、グリーフケアにたどり着いたんです。
グリーフケアとは、大切な人を亡くし、大きな悲しみに襲われている人に対するサポートやケアのこと。その人が死を受け入れ、環境の変化に対応するプロセスを支援するものです。
その中で提唱されていることのひとつが「キューブラー・ロスの5段階」。大切な人を亡くしたとき、喪失から自分を取り戻すまでのプロセスの指標とされているものです。1:否認、2:怒り、3:取引、4:抑うつ、5:受容、この5段階をいったりきたりしながら、人は喪失から立ち直るといわれています。
阿久津さん:「キューブラー・ロスの5段階」を見たときに、まさに自分が辿っている経緯で「あ、これ私だ」と気づいて、それが少しずつ喪失感から抜け出すきっかけになりました。同時にグリーフケアを深く勉強しようと決めたんです。
1年間かけて、グリーフケアを学んだ阿久津さん。その中で、悲しみの意味を見つけ、自分を客観的に見ることができるようになったといいます。
そしてちょうどその頃、東日本大震災が起きました。両親の死を重ね、地震で多くの人の命が失われたことに、阿久津さんは胸を痛めます。
阿久津さん:なんで世の中はこんなに不条理で、思い通りにいかないものなんだろう、と感じました。両親が亡くなり、グリーフケアを学び、大きな地震があって。人生は思い通りにいかない、人は死ぬんだってことを初めて受容したんです。そして、自分が後悔しない人生を送ろうと決めました。
自身の介護を振り返り、「死」を意識していなかったことが反省点だと阿久津さんは話します。
阿久津さん:介護をしているときは、グリーフの知識はなかったので、とにかく生きて欲しい、元気だった元の状態に戻って欲しいと思っていました。生きてほしいから抗がん剤も使ったし、少しでもリハビリになればと思って100マス計算をやらせたりもしました。でも、抗がん剤をしない、薬も飲まない、そんな選択もあったかもしれません。ゆっくり自宅で普通の生活を大切に過ごせばよかった、と今は思います。当たり前の生活が一番大切だと、人は失わないと気づかないんです。
介護にあるのは、「負」のイメージが大きいかもしれません。でも、その先にある「死」を受容することで、最期の時間をいかに大切に過ごすかという意識に変えることができる、という阿久津さんの言葉は、とても力強く響きました。
欲しかったけれど、なかったもの。それは“介護する人への支援やサポート”

両親を見送り、死を受け入れ、後悔ない人生を送ろうという思いに至った阿久津さんは、何かをしよう、何かをつくろうと考え始めます。
阿久津さん:自分が親を介護する中で、必要だったものってなんだろうって考えたときに、「介護する人への支援やサポート」がないことに気づきました。絶対必要なのに、なんでないんだろう。じゃあもう、それを私がつくるしかないなって思ったんです。
こうして阿久津さんが立ち上げたのがUPTREE。「家族介護、一人で悩まないで!」というキャッチコピーを掲げ、家族介護者のサポート活動を行なっています。
家族を介護している同じ立場の人が悩みを分かち合い、「ありのままの自分」でいられる居場所作りを手伝ったり、ストレス軽減のためのワークショップなども開催。
また、今はまだ介護の経験がない、という人が「いつか」のために準備しておけるよう、介護に関する情報を地域のさまざまな人に提供しています。
介護中はどこにも居場所がなく、孤独だった阿久津さんの経験が、私たちがこの日訪れたおれんじなどに繋がっているのです。
おれんじを支えているのは、阿久津さんをはじめとする、UPTREEのスタッフ、UPTREEが主催する「介護者サポーター養成講座」を修了した“サポーター”と呼ばれる方々や、カフェ全体を見守っている店長などです。
サポーターは、ほぼ全員家族の介護経験がある方。カフェの利用者の話にじっくりと耳を傾け、気持ちに寄り添っています。
カフェ全体を見守るおれんじの店長、ゆう屋。さんは、サポーターのみなさんの、本音で話ながらも自然に人に寄り添う姿に毎回胸打たれると話します。

>おれんじの店長 ゆう屋。さん
ゆう屋。さん:サポーターは、介護を経験して辛い思いを乗り越えてきた人たちなんです。そういう人たちと時間を過ごすことで、カフェを利用している方にも変化がありました。認知症の奥さんを介護しているとある男性が、最初は奥さんに冷たい態度をとっていたのですが、ここで何度か時間を過ごすうちに、奥さんへの態度が少しずつ柔らかく、優しくなってきたんです。そんな姿を見て、介護者が気持ちを誰かと共有したり、心を楽にできることが本当に大切なんだなと改めて感じました。
カフェ以外の大きな取り組みのひとつが「介護者手帳」。これは、介護した内容を見える化し、取り巻く状況を見つめ直すきっかけにもなる、介護をする人のための手帳です。「母子手帳の介護バージョン」と言うと、イメージしやすいかもしれません。
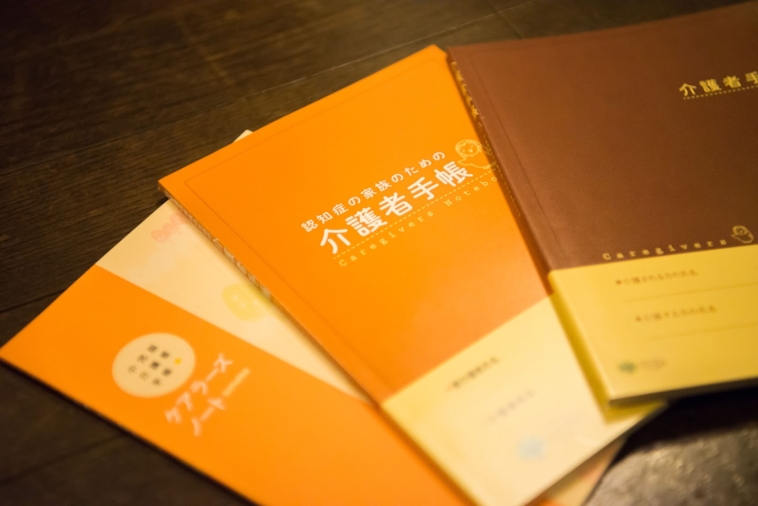
介護の渦中にいると、どうしても目の前のことでいっぱいいっぱいになり、自分や周りの状況が客観的に見えづらくなります。
手帳の中身は、介護全体を把握できるロードマップや、やるべきことやかかる時間を見える化するリストやフローチャートなど。随所に阿久津さんの経験が活かされています。
阿久津さん:介護者にとって大切なことのひとつが客観性だと思うんです。なので、介護手帳を「自分の状況を客観視する」ということに役立ててほしいですね。
客観性意外で大切なのは、100点を目指さないこと、目指すなら50点くらいで十分だと阿久津さんは話します。
阿久津さん:よく相談を受けるのが、介護している家族を怒ってしまう、というもの。でも怒っていいんですよ。家族なんだから当たり前です。もし、アドバイスするなら、「5回怒るなら3回はそのまま怒りましょう、残り2回は優しくしましょう」と言いたいですね。
若いうちから知識と情報のキャッチアップを。それは突然始まるものだから

「介護」と言うと、高齢者の介護ばかりがイメージされるかもしれません。若いうちは、まだまだ遠い世界のこと、という考えになりがちです。でも高齢者介護だけではなく、体や心に不調をきたした家族や大切な人をケアする立場には、誰もがなる可能性があるのです。
阿久津さんが介護を始めたのは、37歳のとき。私が想像していた介護を始める年齢と比べてぐっと早い段階です。しかも、それはある日突然始まりました。
阿久津さん:介護が始まったとき、私はそれについての情報も知識も、全く持っていませんでした。介護には「戦略」が必要なんです。戦略を立てるためには、知識と情報。誰にとっても、ある日突然起きるかもしれないことなので、若いうちから、知識と情報をキャッチアップしておくことが大切だと思います。
とてもドライな表現をすると、介護や誰かをケアするということは、それまで営んでいた普通の生活に、さまざまな「やらなくてはいけない項目」が増えるということ。
その項目を果たすために、それまでの生活を変え、介護やケア一辺倒になってしまう介護者は少なくありません。自分や自分が大事にしたいものを差し置いて、介護中心の生活を送ってはいけないと、阿久津さんはいいます。
阿久津さん:「自分の生活を変えない介護」は、決して不可能なことではないはずです。具体的には、行政のサービス、あるいはUPTREEのようなNPOも増えていますので、専門家はもちろん、家族以外の人の力も借りることが大切です。
若いうちから、介護の大変さや大切さを理解してもらうことを目的として、今UPTREEでは、介護者の目線を教育に取り入れてもらうことを目指しています。
介護者手帳を教科書などに取り入れてもらうことで、介護は大変だけど、とても大切な時間だということを若者たちに伝えたいと考えているそう。
また、若い人に限らず、介護やケアの経験がない人たちへの啓蒙活動として、「介護落語」があります。

阿久津さん:落語家の吉原朝馬さんに、介護の始まりから終わりまでのノンフィクションストーリーを落語にしてもらいました。臨場感があって、経験のない人にとっても、すごく共感しやすいんです。とても好評で、企業研修や自治体からもたくさんオファーをいただいています。リアリティがある、など、落語を見た方からポジティブな感想もたくさんいただきました。
「受容すること」で物事の見方を変えることができる
今は、介護する人を支え、活動の場を広げている阿久津さんですが、介護の渦中にいるときは「なぜ私ばかりがこんなことに」という気持ちを持つことも多かったといいます。
介護や誰かをケアする、ということに関わらず、「どうして私だけが」「どうしてこんなことが」「どうして望むようにならないんだろう」と思うことは、誰にでも経験があるはずです。
阿久津さん:どんなことも、まずは「受容」しないといけないと思います。受容は、他人はやってくれません。自分でやるしかないんです。うまくいかないこと、手に入れられないものに焦点を当てるのではなく、今手にしている「当たり前だけど、大切なこと」に焦点を当てて下さい。当たり前がどんなに大切か。私は両親を失って、初めてそのことに気づいたんです。
「受容すること」で人は、物事の見方を変えることができると阿久津さんは話します。今、そんな視点で思い返すと、弱っていく両親から、それまでとは全く別の愛情をもらったと感じるそうです。
阿久津さんにお話を伺っている間におれんじには、終わりの時間が近づきます。認知症の奥様を迎えに来たという、山口隆さんを阿久津さんが紹介してくれました。
山口さんは、まさに今、奥様の介護をされている方。二人暮しの生活では、なるべく笑わせようと、とぼけた口調で「おはよう」や「おやすみ」の挨拶をするなどの工夫をしているのだそう。山口さんは、思い出話ができなくなってしまったことが悲しいと、それでも、明るい笑顔で話してくれました。

山口隆さん
山口さん:今は随分慣れたけれど、最初はこっちがキレそうになることも度々でした。進行が遅いから助かっているけど、治らない病気だからね。なんでこんなことに、と思うことはあるよ。でも、仕事ばかりの生活で何十年も過ごしてきたから、妻がこうなって、こういうカフェや色々なところで地域の人に会うようになって、初めて地域っていいもんなんだなぁと思うようになりましたよ。
カフェ自体には参加せず、奥様が参加している時間を休息の時間に当てているという山口さん。心や体の休め方は、人それぞれです。
笑顔でカフェを後にする参加者たち。サポーターやスタッフと抱き合ったり、次回の参加を約束したり、参加者の最後のひとりが見えなくなるまで、全員で見送ります。


阿久津さんやスタッフの仕事はここまで…ではありません。参加者が帰った、がらんとした店内で始まったのが反省会。阿久津さんをはじめとするスタッフやサポーターが今日の出来事を報告するこのミーティングは、カフェ終了後2時間に及ぶこともあるそう。

利用者が帰った後に行われる反省会
阿久津さん:ここでは、利用者を支えるのがサポーター。サポーターを支えるのがスタッフです。サポーターもいわば“ケアする人”ですよね。ケアする人をケアしないと、こういう場は継続できないんです。誰かをケアすること、支えることで忘れてはいけないことが、客観的視点で、自分の限界を知るということだから。
ケアする人のケア。優しさは、循環するものだから

“ケアされている人”の一番近くで、もしかしたらその人と同じくらい苦悩しているかもしれない“ケアする人”。
「誰にも理解されないから、と自らシャッターをおろして、介護の話をするのをやめてしまった」と話す阿久津さんのように、私たちのすぐ近くにも、家族や大切な誰かをケアしながら、苦しい胸の内を隠している人がいるかもしれません。
介護の経験がなければ、100%共感することはできないかもしれません。でも、病気や障害がある方、年齢を重ねたおじいちゃんやおばあちゃんだって同じです。
同じ痛みや苦しみや困難を感じることはできなくても、私たちはそっと声を掛けたり、手を重ねたり、背中をさすったりして寄り添おうとしているはず。実はもう、すでにやっていることなのです。
そんなふうに、視野を少しだけ広げ、“ケアする人”の声に耳を傾けて、心を重ねられるようになったら…。
お話を伺ったなかで、とても印象深い言葉がありました。「ケアする人が少しでも楽な気持ちになれると、ケアされる人も楽になれるという循環がある」というメッセージ。
“ケアする人”に重ねた心は、その人を媒介して、“ケアされる人”にも届くもの。そんな優しい“伝染”が社会を包む日がくることを、私は願ってやみません。
関連情報:
NPO法人UPTREE ホームページ
(写真/馬場加奈子)



