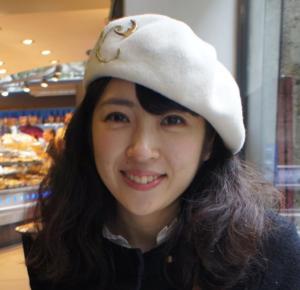生きているなかで出会う、ままならないこと。怪我や病気、仕事や人間関係がうまくいかないことなど大きくても小さくても、様々なことが人生で起こります。
たとえば新型コロナウイルスの感染症拡大の影響で、「これがやりたい」という希望が叶えられなかったり、描いていた未来への見通しが突然に変わってしまう。そんなことも今を生きる私たち誰もが直面している「困難」のひとつかもしれません。
困難を「乗り越える」や「打ち克つ」という言葉を耳にすることもありますが、直面する変化が人生に与える影響があまりにも大きすぎるとき、もはや「乗り越える」という言葉では片付けられない別のあり方が必要なのではないかと感じます。
病気をネガティブなイメージでくくってしまうと、体験を大雑把に抽象化して「自分は辛いんだ」と思わされてしまう感じがする。僕は、「自分の体験は100%自分で味わってやる」みたいな気持ちがあるかもしれません。
小学校6年生で骨にできる悪性腫瘍(がん)の一つである骨肉腫を患い、入院していたときのことを振り返ってそう話してくれたのは、青木彬さん。2019年に片足を切断し、現在は義足で生活しています。
青木さんから出てきた、「乗り越える」や「打ち克つ」ではない、「自分の体験は100%自分で味わう」という言葉の力強さに私は心動かされました。そこには、日々起こるできごとや自分の人生に向き合うヒントがありそうです。
インディペンデント・キュレーターである青木さんは、東京都墨田区でまちを学び場にするアートプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─」のディレクターを務める他にも、まちや福祉の領域で、アーティストや企業、自治体と協同しながら様々なアートプロジェクトを企画しています。

東京都墨田区でまちを学び場にするアートプロジェクト「ファンタジア!ファンタジア!─生き方がかたちになったまち─」の活動風景。(撮影:高田洋三)
主催:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、一般社団法人藝と

多摩ニュータウンを舞台に、まちの遊休不動産や公共空間を活用するアートプロジェクト「たまのニューテンポ」(撮影:コムラマイ)
青木さんは片足切断後、失った右足の痛みを感じる幻肢痛についてや、義足での生活について、ご自身のnoteなどで精力的に発信されてきました。片足切断という、ともすると「困難」と捉えられてしまいそうなことに向き合う青木さんの視線は、とても俯瞰的。自身の体験をフラットに捉え、自分の身体を探求する様子が青木さんの発信からうかがえます。 青木さんが義足になるまでのこと、そして自身の人生に起こる出来事とどう向き合いながら生きてきたのか、お話を聞きました。
12歳で骨肉腫を発症。ネガティブになる選択肢がない8ヶ月の入院生活
青木さんを訪ねたのは春のはじめ。最寄りの駅まで私たちを迎えに来てくれた青木さんが運転する車で、パートナーと暮らす、神奈川県にある住まい兼アトリエに案内していただきました。
アトリエは山に囲まれた自然豊かな場所にあり、心地よい空気と光に包まれていました。
到着してまずあたりをぐるりと散歩して、パートナーと手掛ける畑を見せてもらったり、パートナーが染め物を木に干している様子を眺めたり。

私たちが歩くのと変わらないスピードで歩く青木さんは、「自分の体というよりも自転車に近い」と表現する義足を、乗りこなして歩きます。
ハーフパンツを履いた青木さんの、右側の膝からふくらはぎ、足首にかけては黒い棒が伸びています。地面と接着する「足」の部分は肌色で、甲、かかと、指などしっかりした足の形状をしています。

青木さんは東京生まれの東京育ち。幼少期は、身体を動かすのが大好きな子どもで、小学校時代はバスケットボールに打ち込んでいました。同時に、両親が芸術に関わる仕事をしていたこともあり、母親とは美術館へ、父親とは演劇へ行くなど、生活の中で自然とアートと触れ合い、ものづくりをすることも好きだったと言います。
そんな青木さんに病気が見つかったのは、小学校6年生の春のこと。前年の冬頃から右足に痛みがあり、「成長痛かな」「どこかにぶつけたかな」と思いながら、病院に行ったところ骨肉腫が見つかり、すぐに入院することになりました。
骨肉腫とは、骨にできる悪性腫瘍(がん)の一種です。特に若年者に発症しやすく、成長痛や関節痛、靭帯の損傷などで生じる症状と似ているため、青木さんのように成長痛と勘違いしたままになってしまうケースも少なくないのだそう。
病気が見つかったときはそれなりにショックでした。まだ子どもだったので事態の深刻さが飲み込めていない部分もあったと思うけれど、「バスケットボールができなくなるな」と思ったのは覚えています。
4月から8ヶ月間の入院生活が始まります。治療方法は症状や薬の種類によって異なりますが、青木さんの場合は、1ヶ月に1回抗がん剤を投与し、4〜5日ほど続けて経過観察を行う。その繰り返しで、腫瘍をなるべく小さくしていきました。
抗がん剤投与が始まると、最初は眠らされているのでほとんど意識が朦朧としていて。投与が終わって意識がはっきりしてくると、肉体的にはかなりつらい。髪も抜けるし、吐き気もするし、食べ物も食べられなくて体重が落ちる。だんだん回復して食事がとれるようになると、外泊ができて元気な期間を過ごせます。そしてまた治療が始まる、というサイクルでしたね。
1ヶ月のうち2週間以上は具合が悪い、という生活。12歳の少年が耐えるには過酷すぎるように感じます。お母さんは毎日お見舞いに来て心配していたとのことですが、青木さん本人は、入院中暗い気持ちだった記憶はないと振り返ります。
肉体的にはもちろんつらいんですけど、ボジティブだったからか、周りにも明るいと言われてましたね。同じ病気で入院している子たちと集まってゲームをしたり、病院内を車椅子で走り回ったりして発散していました(笑)
生来のポジティブさに加えて、前向きな覚悟のようなものも伝わってきます。
僕にとってはネガティブになるという選択肢がそもそもなくて。日々やってくる治療を乗り越えて、終わったらこれを食べよう、みたいな楽しみを見つけていくしかない。よそ見して落ち込む暇がなかったんです。

自分の体験は100%自分で味わいたい
前を向いて治療に臨む日々でしたが、一方でお見舞いに来てくれた先生の言葉には、大きな違和感を感じたといいます。
キリスト教系の小学校に通っていたので、お見舞いにきてくれた先生が「神様が守ってくれるから」と言うんです。そういう言葉には子どもながらにすごく違和感がありましたね。副作用の只中にいるのは紛れもなく目の前にいる僕なのに、それを差し置いて神様という存在を出すのは、僕の現実を見てもらえていない気がしてしまいました。
青木さんは、自身の体験を大雑把に捉えられてしまうこと、ネガティブな意味づけをされることに違和感があったのかもしれないと当時を振り返ります。
自分の体験を大切にしていたというか。「病気→入院→悲しい」みたいなイメージでくくってしまうと、体験を大雑把に抽象化して「自分は辛いんだ」と思わされてしまう感じがする。自分の体験は、100%自分で味わってやる、みたいな気持ちでいたのかもしれないですね。
体験を味わい尽くしたいーーその頃から青木さんらしい価値観の表出が感じられます。
ひとり病室で自らの身体と向き合う。そんな日々を過ごす青木さんの当時の支えになっていたのは、アートでした。
演劇関係の仕事をしていた父親が関わっていた舞台で、大人計画の松尾スズキさんが作・演出の『キレイ〜神様と待ち合わせした女〜』というミュージカル作品がありました。すごく好きだったその作品の音楽を、姉がMDに入れて病院に持ってきてくれたんです。それをずっと聴いていましたね。
中でも好きだったのは「物事は割り切れなくてもいい」と歌う曲だったのだそう。
自分が病気をしている状況や、自分と友達、学校、社会の関係に感じていた矛盾とその歌や作品が重なるような感覚があって。芝居が自分の気持ちを救ってくれたという実感があったので、芸術って社会に必要なんだなと思うようになりました。

肉体的につらい状況でありながらも前向きに治療に取り組み、様々な価値観に触れながら自己を形成していったこの時期。入院を経験したことは、青木さんにとってはその後の自分を方向づける、とても重要な出来事でした。
自分の人生を振り返ると、12歳で入院しているときが唯一のひとりで暮らしている時間だったんですよね。ひとりの時間が長かったのと、さらに、抗がん剤治療をしていると、自分の身体と向き合わざるを得ない。
なので、何なら食べられるとか、吐き気がどれぐらいあるとか、自分の感覚や身体の変化に敏感になったんです。自分の身体を客観的に見ている感覚は、そのときに身についたのかなと思います。
手術を繰り返すうちに、脚が曲がらなくなっていった
6カ月の抗がん剤治療を経て9月に手術を行います。膝上から足首までの骨を摘出し、代わりに人工物を入れて骨の代わりにするという手術でした。
退院したのは小学校6年生の11月。春から中学校での新生活が始まるなど大きな変化の中、最初の半年ほどは松葉杖をついて過ごしていました。次第に日常生活にも慣れ、中学校2,3年生の頃には松葉杖も補助具もなく、学校に通えるように。走ることはできず、歩く時も少し足を引きずるような形でしたが、体育の時間にサッカーやバスケットボールなどの運動も出来る範囲でしたり、学校の行事で山登りをしたりなど、運動も楽しめるようになっていました。
しかし、動きやすかった時期もつかの間、今度は成長期のために、足の関節を成長に併せて伸ばす手術が必要となります。中学の終わりから高校の始め頃にかけて、人工関節の金属を入れ替える必要が出てきます。
当時、怪我のリスクがある人工関節よりも、切断のほうがのびのびと運動できるのではないかとの思いから「今から切断という選択肢はあるのか」と医者に相談したこともあったそう。ただ主治医からは「切断の選択はいつでもできるから、まだ残しておいては」との提案を受け、人工関節を使い続けることを決めます。
成長に合わせて足を伸ばせる人工関節を入れて、その後高校時代に2回ほど脚を延長する手術をしました。ただ、手術を繰り返すうちに、人工関節周りの脚の組織が引っ張られて膝の曲がりが悪くなってしまったんです。
曲がりをよくするような手術も試みてみたもののほとんど効果はなく、少ししなる程度にしか曲がらなくなってしまったといいます。
大学へ進学する頃には、角度にして40度程度と、ほとんど曲げられないような状態になっていました。
医師に右足の切断を提案され、即決。でも準備はできていた
ほとんど曲がらない状態になった右足をケアしながら日々を送る一方、大学ではアートマネジメントを専攻し、劇場勤務を経て、キュレーターとして独立します。
定期的に通っていた検診を一度逃してしまったことがきっかけで、2012年を最後にしばらく定期検診に行かず、痛みが出たら痛み止めをのみ、膿が出たら自分で処置するなどして過ごしていました。
状況が一変したのは2019年のこと。石段に足を引っ掛けた瞬間に、激痛が走り、近所の病院から紹介状を書いてもらって7年ぶりにかかりつけの大学病院へ。レントゲンを撮ると感染症が進んでいることがわかりました。
手術をして、このまま人工関節を使い続けることもできるけど、切断じゃない?と主治医に言われました。以前から担当してくれていたから、僕が昔、切断を希望していたことがあるのを覚えていてくれて、今がそのタイミングかもね、と。僕も即答で「切りましょう」と答えました。

切断を即答するーーものすごく大きな決断をあっという間に決めてしまったかのように聞こえますが、青木さんの中ではずっと準備ができていたのだと言います。
人工関節が入った足で、一生生きていけるとはどうにも思えなかったんですよね。だからどこかで自分の身体のステージが変わる予感はあって。切断を提案されたときに、どこか肩の荷が降りたような、もう頑張らなくていいんだ、やっと次のステージにいける、という感覚があったんです。
日々自分で右足を労りながら生活する中で、次のステージとして、切断を選ぶというのは青木さんにとって自然な選択だったのでしょう。また骨肉腫ができてすぐに切断するのではなく、人工関節を入れていたのも必要な時間だったと話します。
12歳で足を切断するとなっていたらその状況をポジティブに捉えられていたかはわからないです。そういう意味でクッションになっているのが、人工関節の期間だったのかなと思います。

2019年11月。足を切断する手術をし、1ヶ月の入院をします。退院してほどなくすると、義足をつくる病院に10日ほど入院。義足をつけての生活が始まります。
どんな生活の変化があったのかとたずねると、とても明るい調子で「すごく元気になった」と話してくれました。
今まで炎症反応があって、ずっと風邪をひいているみたいな状態だったのがなくなったというのがまずあって。それから、人工関節が自分の体から無くなったことで、身体的にも100%自分の身体になった感じがありました。足が曲がらなかったため、体育座りのようなポーズがずっととれなかったんですね。足を切断してから、お腹の中の赤ちゃんみたいに体を中心にぎゅっと集めて丸まることができるのが嬉しくて。
心身ともに元気になって、周りの人からも手術後のほうが顔色が良いと言われるように。
義足をつけ始めてからは今まで以上に痛みもなく、歩くことも不自由なくできるようになりました。
「12歳の頃に入院してからずっと乗っていなかった自転車にも乗れるようになって、長距離を歩くことができるようになりました。今は生活のために必要なので車も運転するようになった」
そう話す青木さんは楽しそうで、足を失うことは、青木さんにとって喪失というよりもポジティブな体験だったように感じられます。
楽しみが多かったんですよね。かっこいい義足をつくりたいとか、半ズボンを履けるとか。

さらに義足になることで、病気や障害が目に見えるものとして、オープンな存在になったという変化もありました。
今まで病気自体をネガティブに捉えることはなかったのですが、あまりオープンな存在ではなかったかもしれません。それでも痛み止めを飲んで、ガーゼを変えて…などの日々の負担にストレスはあったから、それを包み隠さなくていいという心理的な負担の軽減がありました。
noteを書き始めたり、義足として見えるかたちになったことで、今までつながることがなかった人たちとつながったり、それを通してコミュニケーションが生まれたのはよかったなと感じています。
幻肢痛への好奇心と探究心
青木さんは自身のnoteの中で、「無いものの存在」として、右足を切断をしたことや体験している幻肢痛について細やかに描写しています。
幻肢痛とは、失ったはずの手や足がまだあるように感じ、その部分に痛みを感じること。手や足を失ったことに対して、脳が正しく適応できなかったために生じると考えられていて、通常の鎮痛薬などでは治療できずに、また有効な治療法は確立されていないのだそうです。
切断をしてすぐに始まったという青木さんの幻肢痛の症状。一体どのように変化していったのでしょう。
切断後にベッドに戻ると右足がものすごく熱くて。麻酔で朦朧としながら手術は失敗したんじゃないかと感じるぐらいに右足の感覚がありました。それから数日経ち、手術の痛みが落ち着くにつれて、切断したはずの右足の延長上に続きがちゃんとあるように感じられて。
ベッドから降りて車椅子で動くようになってからは、痛みや感覚がずっとあるというよりは、急にどこかかゆくなるような感じでした。一箇所だけ、切断されたはずの足のところが急に輪ゴムをはじいたようにパチン!と痛くなったりしていました。

感覚が続くうちに、幻肢痛に薬が処方されるようになります。ただ青木さんの場合は薬を飲むと意識がぼーっとしてしまい、体質に合わないと感じたこと、さらに「無いものの存在」にもっと耳を傾けたいと思ったことから、薬剤師さんに相談のうえ、薬を飲むのをやめるようになります。
病室に来た薬剤師さんに「部位がないから痛み止めを飲んでも効くことがない。それなら僕が飲んでいる薬は何をしようとしているのか」と聞いたんです。要は、頭の神経を落ち着かせるために飲んでいるとのことでした。
部位がないのに感覚があるってことは身体が何かしら発しているわけだから、僕はその声にもっと耳を澄ませたいと思ったんです。
同時に青木さんは、幻肢とコミュニケーションを取り、困難の当事者自身が自らの研究者となって自分を助け励ます方法を考える「当事者研究」的に幻肢痛と向き合います。
痛みがあるところを擦ってみたりして、痛みを和らげる方法は色々と試してみました。さらに幻肢を伸ばして50m先を感知するなどコントロールができたら面白いなと思って。
その結果、残念ながら痛みをおさえることや意識して形を変えることはできませんでしたが、気づいたことがあったそう。
意図的に形を変えることはできないけれど、環境でコントロールできるということはわかってきました。例えば、切断したばかりの頃は、座ると普通はまっすぐ前に伸びるはずのところ、幻肢はちょっとしなるような感じで下のほうが痛かったりするんです。でもちょっと角度をつけるとまた幻肢の向く方向が変わっていく。幻肢もどうやら重力を感じているようだな、などとわかるようになってきました。
それにしても、幻肢痛という痛みがあるだけで、肉体的にはかなりの負担がかかっているはず。その痛みを感じながら、研究対象として向き合う青木さんのあり方には驚かされます。「痛み耐性が強いんだと思います」と笑いながら、こう話してくれました。
幻肢痛というのがあまりにも強烈な体験すぎて、痛みを好奇心が上回ってしまったんです。学生時代に読んだ哲学書で幻肢痛について知っていたのですが、その本を書いている人たちも実際に幻肢痛を体験してはいないわけで。それを自分が経験できることにワクワクしましたね。

「大人ってこれでもいいんだ」アートに救われた体験
経験をすることにとても前向きで、体験を味わい尽くす青木さん。足を切断するという失うものよりも、義足でできるようになることや、幻肢痛、義足をつくることなど新しい体験にワクワクしています。
自分の体を信用していたこともあるし、工夫することも好きなんです。
そう話す青木さんの根底に自分への信頼感と、好奇心や探究心があることが感じられます。

「幻肢を観察することも、コントロールしてみようとすることも、その思考や想像力という技術の扱い方は基本的に自分のキュレーションの技術に援用することができないかと考えている」
[無いものの存在]_10:目の前の人に幻肢がぶつかる より
青木さんのnoteを拝見していると、アートに向き合うような姿勢で貪欲に経験し、そして経験したことをアートの手法に生かす、という、「自身の経験」と「アートの考え方」への往復があるように感じられます。
青木さんの価値観や考え方の軸ともなっているように見える、アートの原体験とは、どのようなことだったのでしょうか?
最初の入院中に、ミュージカル作品の音楽をMDで聞いていたと話したんですけど、その作品を観たのは小学校3年生ぐらいだったんです。父親が大人計画の舞台に関わっていたので、僕にとってはアンパンマン、ウルトラマンの延長に大人計画がある、というぐらい身近なもので(笑)
大人計画はブラックジョークや風刺を効かせた作品も多くて、当時は子どもが触れる世界としては過激なところもあったんですけど、舞台上の役者さん達や、毎日楽しそうに仕事している父親の姿をみたときに「大人ってこれでもいいんだ」って。子どもながらに救われた気がしました。
子どもにとって、大人の姿は未来。いわゆるアニメに出てくるような、子どもに注意ばかりしている「大人」の像に当てはめなくてもいい。多様で魅力的な人の存在に舞台を通して触れることや、アートの現場で働くお父さんを見ることは、青木さんが未来への希望を感じる瞬間だったのかもしれないと感じました。
一方で、青木さんの中に根付いている、アートのものの見方が今回の経験に生かされていることもあるのでしょうか。
物事にいろんな選択肢があるということを感じられたのは、アートに触れていたからかもしれません。病気をしていて、社会的に障害者と呼ばれることは、ネガティブなことだと思い込みそうだけど、自分でその選択をしなくてもいい。
さらに同じ病気をしていても、実際入院している人のリアリティってそれぞれ違う。だから一つの解釈に落とし込まなくてもいいというのは強く感じています。
そうした多様なものの見方ができるということが、「どんな状況になっても大丈夫」と思える、青木さんの揺らがない自分自身への信頼感につながっているのかもしれません。

“障害の当事者”であるという個別性を、どこまで出すのか
アトリエでインタビューをさせていただいた春のはじめの日から10ヶ月。再びお話を伺おうとオンラインで対面すると、その後心境に変化があり、「言語化しづらいけれどモヤモヤしていることがある」と青木さんは話し始めました。
自分について言語化することへの迷いが生じていて。まだアウトプットするというよりは、自分の中で考えていきたいなというのがあったので、noteを書くのを止めているんです。
小学生の頃に骨肉腫を患った青木さん。人工関節を入れ、障害者手帳を持ってはいたものの、症状が見た目にはわかりづらいことや、自身が積極的に発信してこなかったことから、障害者としての当事者性を意識することはあまりありませんでした。ですが、義足という目に見える形になり、noteを通じて発信することで、周囲からもその当事者性を認識されるようになります。
自分の体験を伝えることで、ケアや福祉の領域で声をかけてもらうことが増えたことによって、自分もそうしたテーマについて考えられることが増えたのは嬉しいんです。ただ自分が、“障害がある人”としてカテゴライズされていくときに、義足当事者であるという個別性の出し方のチューニングを誤ると、自分が考えていた方向ではないところに行ってしまうような気がしていて。
右足の切断や幻肢痛といった個別性の高い経験を発信することは、青木さん自身にとって“未知で不定形だった体験”がパッケージング化されていく感覚でもあったのだそう。それにより、ほかの人たちが立ち入る余地をなくしてしまうのではないか、という懸念のようなものを青木さんは感じているようでした。
僕は幻肢という自分でもわからないことを、ただ「わからないこと」として語ってきました。そこから「わかる」ことなんて一つもないと思っている。でも、義足の障害者であるという個別性を持った僕が発信をすることが、誰かの問いを「こうです」と断定してしまうことになるんじゃないかという気がしたんです。
義足は個別性が強いことだと思うので、自分にとってはそれが興味深いんだけど、そこを強めすぎるとその個が際立ってしまうことも不安で。
青木さんは、自分にとってのアートを「個の表現(個別性)と公共のもの(普遍性)がつながっていくこと」と表現します。そうした考えを持っているからこそ、社会に向けてどのように自分の個別性を開いていくかを悩み始めました。
自分のアイデンティティを出していくことが、自分を苦しめているかもしれないな、今の自分はうまくそれを使いこなせてないなっていう気がして、その出し方についてもうちょっと考えたほうがいいかなと思うようになりました。

個人の主観的な体験や、小さな物語を大切にしたい
個人の主観的な体験を、どう語るかーーこれは青木さんがキュレーターとして、個の表現という小さな物語と、アートの歴史やジャンルといった大きな流れという双方に向き合う立場だからこそ、考えるところもあるのだとか。
例えばアートでも、主に障害のある人などが取り組むアートとされているアウトサイダー・アート分野でも逡巡することがあります。僕も現場で作品をつくる人とお話をさせてもらうこともあるのですが、そうした創作活動はその人の個別性が強く出ますし、さらにその経緯や取り組み方、発表の仕方などは横にいる支援者の方との信頼関係があってこそ生まれている。
ただそれをアートの手法にのみ着目し「アウトサイダー・アート」としてまとめると、全然違う文脈が開かれていく。もちろんそれはそれで可能性があることだと思うけれど、そのアートを生み出した個人の特別な体験に目が向けられなくなってしまうかもしれない部分もあると思うんです。
社会の大きな流れのなかでも、主観的な体験や、小さな物語を大切に捉えたい。青木さんがそう考えるのは、子どもの頃からずっとヒップホップが好きなことが関係しているかもしれないといいます。
12歳で病気をした頃にヒップホップを聴き始めたんですよね。ラップは言葉でリズムをつくっていくというのが、当時見ていた舞台のセリフの延長のようにも感じられて面白かった。
あとは、入院して、社会から断絶されてマイノリティになっていく感覚を覚えたときに、いわゆるポピュラーなヒットソングの抽象性が自分にはなじまなくて。
ヒップホップって、ものすごく個人的なことを歌っていることが多い。
例えばZeebraの『真っ昼間』って、朝遅めに起きてシャワーを浴びて出かけるって内容なんですけど、それが“俺”が見てるこの街を捉えた、一種の私小説のように僕には感じられたんです。
普遍化はしようとするけれど、まずは自分のことから語っていく。僕は個別性があるものが好きだし、その人の存在に触れられると安心するんですよね。
青木さんはモヤモヤを抱えながら、自身の身体、思考、アートや音楽などの関心ごとなど、様々な角度から自分を捉えなおして、自分自身を探求しているようにも見えました。だからこそ、自身が進めるアートプロジェクトにおいても、自己を開示する塩梅がわからなくなり、プロジェクトを進めること自体が一時うまくいかなくなってしまっていたとのこと。ですが、モヤモヤについて考え、言語化し、周囲に伝えていくことで、状況は変化していきました。
こういった話をまず周りの友達にしたら、モヤモヤも含めて、言葉にして発信してほしいって言われて、確かにそうだなって。思えばこの半年ほど、僕がディレクターを務めていた事業の中で悩んでたことも、周囲には共有できず僕だけ抱えてしまっていた状態だったんですよね。でも悩んでますって言ったほうがいいなと思って、最近は気持ちを抱え込まないようシフトしていっています。
そうして2022年3月に久しぶりに更新された青木さんのnoteのタイトルは、「わからないことをわからないまま」。迷っていることや、書きたくないということさえもそのままに、再びnoteに綴り始めました。
義足づくりを通して右足を供養する
最近は、モヤモヤを抱える中でストップしていた義足づくり(本義足のソケット部分の加工)も再開されたのだそう。もう一度取り組めるようになったきっかけはあったのでしょうか。
それがあまり深く考えずにできたんですよね。ふと描けるかもと思ったから、パートナーに描く?と言って、二人でブレストして落書きみたいなのをしながら、それをもとに一緒に描きました。モヤモヤしている間はどんなマインドセットで取り組めばいいのかわからないでいたのですが、それをやったときに、これくらいでいいんだよなって思いました。

無理をしないで自然な流れでできた、そのことがよかったと青木さんは話します。
義足には、育てた藍を使って染色した布、切断した右足の骨の遺灰を入れて漉いた紙を使い、さらに遺灰を顔料にして布に絵を描くなどしてつくっています。
ちょっと変わった義足のつくりかたは、青木さんが「義足自体が歩くことを喜ぶような義足をつくりたい」と考えたことがきっかけでした。
自分が踏む地面の土でできた植物で染めたものと、僕の右足の骨をソケットに組み合わせて、新しい右足というか、自分の体を作ろうと思ったんです。自分だけが快適というよりも、義足自身も楽しくなるような。
青木さんの切断した右足はその後火葬したそうですが、その遺灰が入った骨壷を受け取ったときには、それをどこか距離のあるものに感じていました。けれど、今回布に遺灰で絵を描くことが、もう一回義足として自分の身体に戻していくという儀式となり、「自分の身体を失っていない」という感覚になったのだと言います。
自分の骨を材料にして義足をつくっていくことに、自分はポジティブだったんです。でも、“自分のポジティブ”のために足を切断したかのようで、そのことは小骨みたいにどこか引っかかっていたんですよ。でもこの前、遺灰を顔料にして布に絵を描いていたときに、右足が供養されたような感覚がありました。

足を切断したあと、幻肢痛を体験し、自分の義足を自分でつくり始めた青木さんは、そのプロセスによって改めて自分の身体の存在を確認しているといいます。
幻肢痛は最近は感じ方がランダムなんですよね。ビリビリと痛みを伴うこともあるし、ボヤッとしていることもある。でもいつでもそこにあるという存在感があるんです。
だからその幻肢の感覚と自分の体だったもの、今の自分の周囲にある環境が重なりながら義足が出来上がることで、その足は自分が100%自信や信頼をおける身体になるという感覚があるんです。
遺灰を使うことで、物質的にも足が身体に戻っていって、一方で幻肢の存在もなくなっていないから自分の身体としての実感もあるはず。多くを求める必要はなくて、それで十分だなと思えたし、むしろそんなこと迷わずにできるはずがない。だからモヤモヤすることがあって当たり前だし、そういう不安やモヤモヤも含めて共有してもいいんだと思えたので、もう一度安心して取り組むことができるようになったのかなと思います。

アーティストやアートに関わる方の話を聞いたり、作品を見たりするときに感じるのは、「面白がる天才だな」ということ。目の前にある素材、人、場所をよく観察して、特徴を発見して、感性や知識を総動員して形にしていくーーそこには俯瞰の視点と、面白がる向き合い方があるように思います。
「自分の体験は100%自分で味わいたい」
そう話してくれた青木さんの、病気や足を切断した体験との向き合い方には、青木さんのアートへの向き合い方に似たものを感じます。
困難を前にして、「どうしてこんなにうまくいかないんだろう」と胸がザワザワするときもあるけれど、試しに青木さんのように「この状況をどうやったら味わい尽くせるだろう」と考えてみるのはどうだろう。そこにあるのは困難ではなく、まだまだ面白がれる私の人生だーーそんなエールを青木さんのあり方から受け取りました。

(撮影/川島彩水、編集/工藤瑞穂、企画・進行/松本綾香、協力/佐藤みちたけ)