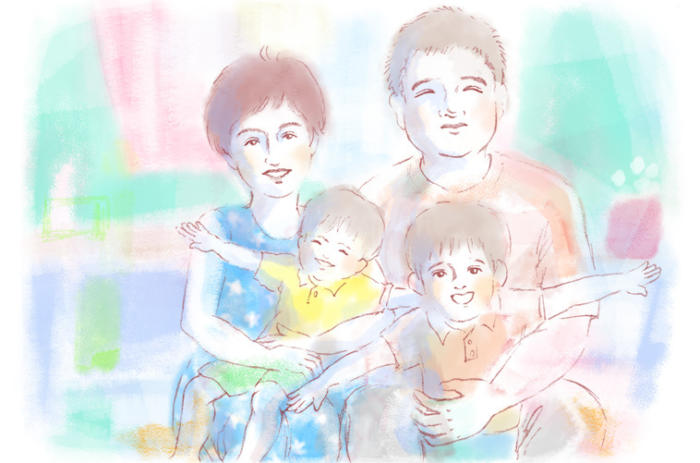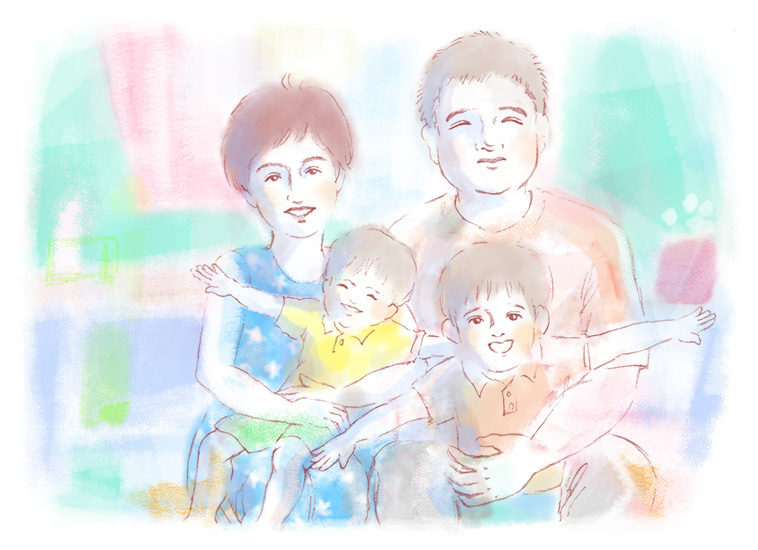
他者からのイメージと自分の気持ちとの間にギャップを感じたり、「こうあるべき」という姿に自分自身でしばられてしまったり……。他者の評価に揺れ、社会の空気を感じとって生きるうちに、私たちは「自分とは何か」を見失いそうになることがあります。
自分のアイデンティティは自分で決めればいい。
今はそう話すナディさんも、他者との違いに悩み、自分のあり方に葛藤しながら人生を歩んできました。
イランで生まれ、6歳から日本で育ったナディさんは、見た目から「外国人」扱いされることも多く、一時期は「イラン人」と「日本人」の間でアイデンティティに揺れたこともあったと話します。「ずっと周囲や自分自身が描くイメージに縛られていた」と話すナディさんの思いには、たとえ育ってきた背景は違っても共感するところがたくさんあるように思います。
昨年6月に出版された『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』(大月書店)には、ナディさんが家族で日本に来てからの体験や思いが率直に綴られています。ナディさんが高校生のときに一家は在留特別許可を得ましたが、それまでの間は在留資格(※)のない、いわゆる「不法滞在」として生活していた時期もあったそうです。
私たちは多くの外国ルーツを持つ人たちと一緒に暮らしているはずなのに、日本でどう暮らし、どんな思いを感じているのかを話したり聞いたりする機会がほとんどないということにも、ナディさんの本を読んであらためて気づきました。2019年末時点で、在留外国人の数は293万以上。また、日本国籍をもち日本以外の国にルーツをもつ人を加えると、その数はおよそ400万人にもなります。
日本で暮らして29年。日本とパラグアイのルーツをもつパートナーと結婚し、現在は仕事と2児の子育てと、とても忙しい日々を送っているナディさん。アイデンティティの葛藤を乗り越えて、どのように自分自身を見つけていったのでしょうか。これまでの思いや、いま大切にしていることについて伺いました。
※在留資格:日本の入国管理局が与える、「永住」「留学」「技能実習」「家族滞在」など、それぞれの活動に応じた滞在許可のことを「在留資格」と言います。在留資格には期限がありますが、その期限を過ぎても滞在することを「超過滞在(オーバーステイ)」と呼び、法律上はすぐに出国しなくてはならず、施設に収容されて強制送還されることになります。しかし、さまざまな事情によって日本を出ることのできない人たちもいます。そうした事情を考慮し、例外的に法務大臣から「在留特別許可」を得ることができれば、新たな在留資格が交付されます。
6歳でやってきた「みなしごハッチ」の国
まだ6歳だったナディさんが日本に来たのは1991年のこと。ご両親に連れられて、2人の弟もいっしょでした。ナディさんには、4歳のときまでイランで続いていた戦争の記憶がいまも残っています。
とても怖かったので、よく覚えているんです。トラウマみたいな感じですよね。日本に来てからも甲子園のサイレンを聞くと「空襲!?」と思って怯えてました。
ご両親はもともと裕福な家庭の出身でしたが、戦後の混乱のなかでイランの経済が安定せず、運営していたお店に泥棒が入るなどもあって、大きな借金ができてしまいます。そのため、ナディさん一家はいわゆる「出稼ぎ」のために日本に来たのです。
当時、イランからは事前にビザの申請をしなくても、入国時に短期の観光ビザが発行されていました。好景気だった日本では、「3K(きつい、汚い、危険)」と呼ばれて日本人が敬遠していた仕事を低賃金で働く外国人労働者が担っていました。今ほど取り締まりが厳しくなかったこともあり、在留資格がないまま働き続けている人たちが多くいたのです。
ナディさん一家も、観光ビザでの入国でした。入国の際、ナディさんの父親は空港職員から「あなたの家族が働きに来たということはわかっている」と言われたそうです。
実は、イランにいるときに、テレビで日本のドラマ「おしん」や「水戸黄門」のアニメ、「みなしごハッチ」などがペルシャ語で放送されていました。6歳の私は、世界にはイスラム教徒の国しかないと思っていて、水戸黄門もきっとイスラム教徒で、日本でもみんなペルシャ語を話すものだと思いこんでいたんです。だから、不安というよりもテーマパークに行くような気持ちでワクワクしていたんです。
しかし、実際に日本に着いてみると言葉は全く通じず、ナディさん一家が住むアパートにいたイランの人たちでさえも、あまり歓迎ムードではありませんでした。
他のイラン人はみんな単身で、家族ぐるみで来日していたのは私たちくらいだったから、すごく珍しかったのです。ビザの期限が過ぎていることが警察に分かるとイランに強制送還されるかもしれないので、小さい子どもたちがいると目立ってしまうのではないかとみんな心配していました。
まず覚えたのは「ニコッ」と「ペコリ!」
そんな右も左も分からない状態から、日本での生活がスタート。学校に通えるような状況ではなく、ご両親は朝早くから夜遅くまで工場で働いていたため、その間はナディさんと弟2人で留守番をして過ごさなくてはなりませんでした。まず覚えたのは「ニコッ」と「ペコリ!」だったと言います。
アパートで人に会ったら、とりあえずニコッと笑顔になる。そしてペコリ!とおじぎをしました。そうすると相手も笑顔になるので、言葉が通じない不安が和らぎました。誰もいないときを見計らってアパートの向かいの公園で遊ぶとか、人目につかないように自分たちはすごく気を付けていたつもりでしたが、日中に子どもが3人でいたので、実は近所では目立っていたみたいですね(笑)。
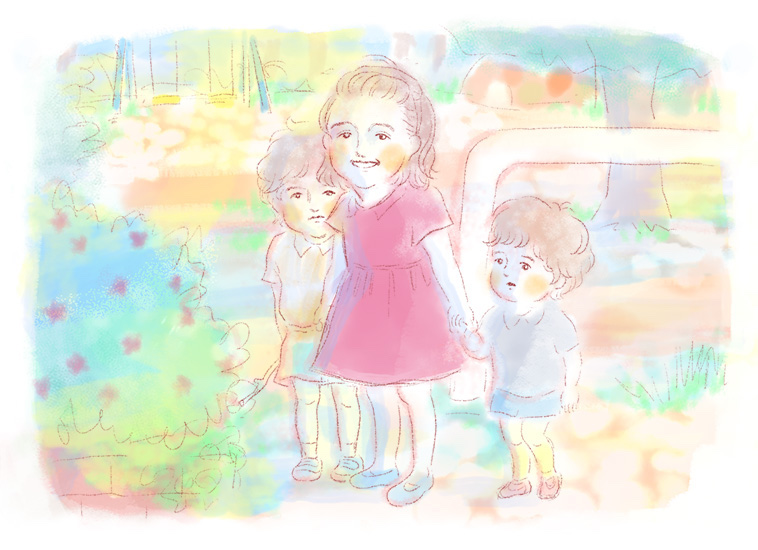
本当だったら、まだ親にわがままを言ったり、甘えたりするような年齢。ナディさん自身はどう感じていたのでしょうか。
仕方ないですよね。甘えたくても、そういう環境ではなかったですから。公園で友達になったほかの子どもたちを見て、「いいな」とは思いましたけど、子どもってすごく空気を察するので、「よそはよそ。うちは違うから」っていつも思うようにしていました。
それでも、公園で子どもを遊ばせているお母さんたちが、ナディさん姉弟の分までおやつを持ってきてくれたり、仲良くなった近所の女の子のご両親が折り紙やあやとり、平仮名やカタカナを教えてくれたりしたそうです。
もちろん、いい経験ばかりではありませんでした。公園で仲良くなった女の子と歩いていたら、その子のおばあちゃんが「外国人と遊んじゃだめよ!」と大声で言ったこともあります。外国人だから知らないうちに何か悪いことをしてしまったのかな……とか、本当は周りの人も「外国人だから悪いやつ」と思っているのかな……と、すごく悲しい気持ちになりました。
さらには、家の玄関から石やごみを投げ入れる男の子たちもいました。ナディさんの母親が怒って、そのうちの一人の男の子の家に文句を言いに行き、ナディさんがそれを通訳をすると、相手の父親は顔色を変えて子どもに謝らせ、ほかのいじめっ子の家を一緒に一軒ずつまわって叱ってくれました。
実は、それ以来、その子どもたちと仲良くなって一緒に遊ぶようになったんですよ。「外国人だから」ではなく、悪いことは悪いとおじさんが言ってくれたおかげです。
先の分からない生活に疲れて……
そうして、だんだんと日本の暮らしにも慣れ、日本語も覚えていったナディさん。さまざまな人の支援によって、10歳になった時にようやく小学校に通えるようになります。当初は3年でイランに帰る予定でしたが、日本語を覚え始めた子どもたちの教育のことを考えて、ご両親は悩んだ末に日本に残ることを選びました。
小学校には公園で遊んだことのある友達もいて、スムーズに溶け込めたというナディさん。ただ、漢字が読めなかったため、教科書やプリントに何が書いてあるのか分からず、勉強に追いつくのは大変でした。また、成長するにしたがって「自分はイスラム教徒だ」という意識が芽生えるようになると、肌を露出するブルマや水着を着ること、給食に豚肉が入っていることなどが気になり始めます。
給食を残さないというのは、学校では絶対のルールみたいなものだったので、豚肉を残していいかとか、ブルマではない体操着で体育の授業を受けてもいいかとか、担任の先生に聞くのもすごくドキドキしました。でも、先生はあっさりOKしてくれたんです。みんなと違うといじめられるのではないかという不安もありましたが、さいわい周りの友達も受け入れてくれました。
周囲の支えもあってナディさんは学校生活を続けることができましたが、中学に進学してからも、在留資格がないことでの不安や不便はいつもつきまとっていました。たとえば、健康保険に加入できないため、ケガや病気で病院に行くと治療費が非常に高額になります。そのため滅多なことでは病院に行かず、足の骨にヒビが入って足がパンパンに腫れるほどになっても、痛みをこらえて学校に通ったこともありました。さらに、警察に捕まったり、強制送還されたりする可能性がつねにありました。
当時は、いまと違って不法滞在だと分かってもすぐに強制送還されたわけではありません。それでも、不法滞在のまま生活するということは一寸先が分からない生活が何年も続くということ。日本になじむ努力をして、なんとか受け入れられても、強制送還されればすべて水の泡です。
来年、来月、もしくは来週でさえ、いまと同じ場所での生活を続けられるのか分からない――そんな状態では将来のことを考えることもできません。ナディさんは高校受験へ向けた準備を始める時期になっていました。
そんなとき、新聞で外国人労働者を支援する団体が「在留特別許可を求める外国人家族の一斉出頭」を主導していることを知り、いちかばちかナディさん一家は入国管理局に出頭することを決断します。在留特別許可を得ることができれば、合法的に日本で暮らせるようになりますが、審査が通らなければ待っているのはイランへの強制送還。それでも、「もう不法滞在はいやだ」という思いの方が強かったのだとナディさんは振り返ります。
入国管理局での審査結果はなかなか出ませんでしたが、その間にもナディさんは第一志望の公立高校に見事合格。そして、出頭から1年半以上経ったある日、ナディさんたち一家全員に在留特別許可が認められました。
ナディさんたちが、その足で向かったのは市役所。念願の健康保険に加入するためでした。
「イラン人」でも「日本人」でもない自分
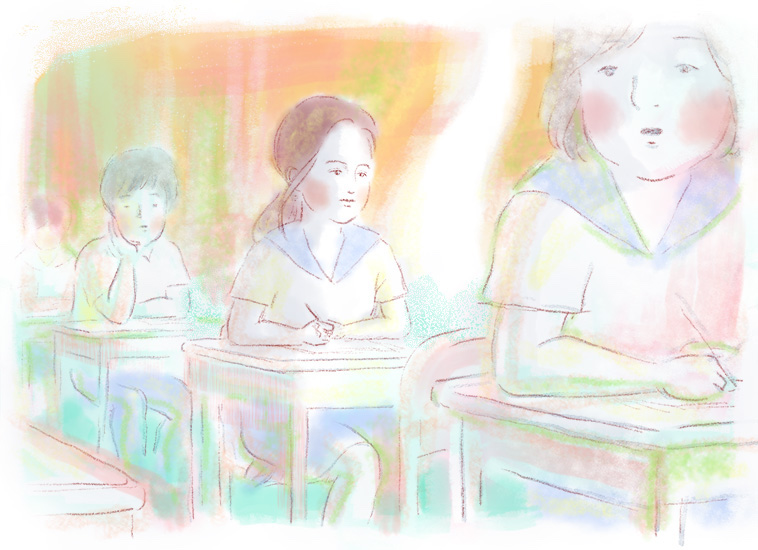
日本に来て11年目で、ようやく日本に住み続ける許可を得たナディさんですが、その後「自分は日本人でもなく、イラン人でもない」というモヤモヤした思いに長期間悩み続けます。
これは外国ルーツをもつ人にとっては「あるある」だと思うんですけど、イランから来たというだけで、学校の同級生から、まるでイラン人の代表のように扱われるんですよね。イラン対日本のサッカーの試合があったら、代表チームについて聞かれたり……。
6歳から日本にいるから、よく分からない。それでも一生懸命調べて教えたりしていました。最初はそんなものだと疑問に思わなかったのですが、だんだんと周囲の目線と自分の気持ちの間にギャップを感じるようになっていくんです。
見た目から「日本人」として見てもらえない一方、11年ぶりに祖国イランを訪れた際にも、振る舞いが違うために「どこから来たの?」と外国人扱いを受けてしまいます。
ずっとイラン人らしいイラン人をイメージして、「自分はそうならなくちゃいけない」と思っていました。でも、ほとんど日本で育った私には無理なこと。かといって、どんなに「日本的」だと言われても、見た目で日本人ではないと判断されてしまう。街を歩いていてジロジロと視線を感じることもありますし、アルバイトの面接で「外国人はちょっと……」と言われたこともありました。
そんな「イラン人でもなく、日本人でもない中途半端な自分」という思いを変えてくれたのが、外国ルーツの子どもたちを支援する団体で知り合った友達の自己紹介でした。
ずっと前から知っていた友達だったのですが、あるとき自己紹介で「モンゴル人に見えますが、日系アルゼンチン人です。アルゼンチン人のアイデンティティを持っています」と言っているのを聞いて、ハッとました。
私は自分の顔立ちが日本的でないことに悩んでいましたが、その友達は「自分」という人間がいくつもの要素を含んでいることを前向きに受け止めていた。そのとき、自分が描く「イラン人」や「日本人」に100%あてはまらなくても、自分のアイデンティティは自分で決めていいんだと気づいたんです。
ずっと「こうあるべき」という姿に縛られていたと話すナディさん。「イラン人だったら、こうでなくちゃいけない」「日本人だったら、こうでなくちゃいけない」と考えていたのは、すべて自分が勝手につくっていたイメージだったのだと気づいたそうです。
いまナディさんは「イラン生まれで日本育ち、中身はほぼ日本人のイラン系日本人。これが私」と話します。
「自分がどうありたいか」よりも、他人の目線や自分が作り上げたイメージに左右されていました。たとえば、日本人かどうかを判断するのに、日本にいる期間にこだわる人もいれば、見た目にこだわる人もいます。私のことを「そんなに長く日本にいるなら日本人ね」と言う人もいれば、「日本人じゃないよ」と言う人もいる。その度に相手の意見に揺れていたんです。
でも、自分のアイデンティティは自分で決めればいいことなんですよね。つい「みんなの意見のほうが、自分よりも正しいんじゃないか?」と思ってしまうのですが、「単純に自分はどう感じるの?」と、まず自分に聞いてみることが一番。そして、「自分はそうじゃなくて、こう思うんだけど」って伝えること、そう言える環境や関係性も大事だと思います。
「当たり前」が「当たり前」とは限らない
ナディさんは『ふるさとって呼んでもいいですか』の本を出版して以来、さまざまなメディアや講演会などでの発信を続けています。
「不法滞在者」というと「キケンな人」というイメージがあるかもしれませんが、私のような6歳の子どもだっているし、ごく身近にいる「普通の人」なんだと言うことを知ってほしくて話をしています。
しかし、この本を出す直前まで、ナディさんは「自分は特別に日本にいさせてもらっている身だから」、何かを主張してはいけないんじゃないかと感じていたそうです。
その考えが変わったのは、望月優大さんの『ふたつの日本 「移民国家」の建前と現実』(講談社現代新書)という本を読んだから。日本が政策として外国人労働者を受け入れてきた歴史について知りました。
不法滞在はよくないことですが、そこには日本が外国人労働者を必要としていたという背景もあった。いまは留学生や技能実習生へと形は変わっていますが、やっぱり多くの外国人が日本で働いています。遠慮して黙っているのではなく、この国で生きていく一人として、自分の体験や思ったことを伝えてもいいのではないかと思えるようになりました。
本を出したときは、批判的な意見も覚悟していたというナディさんですが、実際には「よく頑張ったね」と言われることも多かったそうです。
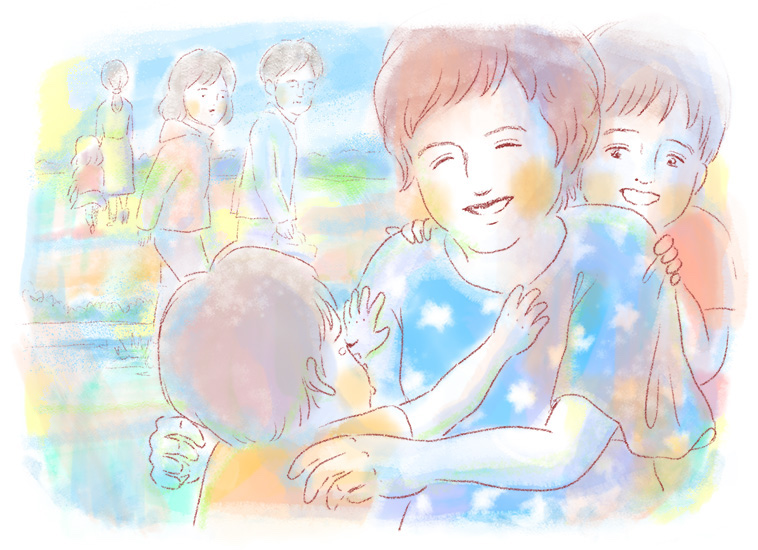
それを聞いて嬉しい反面、もし「頑張らなかった私」だったら、どうだったんだろうとも思いました。私は、ずっと「自分は外国人だから、日本に気に入られないといけない」と思って「いい子」でいようと振舞ったし、たまたま得意だったので勉強も頑張れました。
でも、別に勉強ができなくても、いい子じゃなくても、言葉がよく分からないのに学校に行くだけでもすごいことだし、生きているだけで充分。そのことを子どもたちには伝えたいんです。
2歳と4歳の子育て中でもあるナディさんは、最近とくに「当たり前だと思っていることが当たり前とは限らないことを、小さい頃から伝え合える環境をつくること」の必要性を感じていると話します。
たとえば、日本の学校では「1+5=X」のXが何かを考えさせますが、それだとXの答えはひとつしかないですよね。でも、「■+●=6」という形で、何通りもある組み合わせを考えさせるやり方もできます。Xを考えさせるのは合理的で速いかもしれないけど、いろんな考え方があって正解はひとつではないことを、子どものうちから教えることが大事だなと思うんです。
小さい頃から「アメリカ人なの?」と聞かれたり、「英語が話せるの?」とよく聞かれてきたというナディさん。「外国人=アメリカ人」、「外国語=英語」が当たり前、と思ってしまうのは、教育の問題ではないかと感じています。
そういうのって、女の子はピンクで男の子はブルーだと決めつけるのと同じようなもの。それ以外の見方もあるんだよ、と子どもたちが教わる機会がない。せっかくランドセルもカラフルになってきたのだから、もっといろいろな見方があるってことが広がればいいなと思います。
ナディさんは、これから日本で育っていく自分の子どもたちの将来にも思いを巡らせます。
前に息子と散歩していたら「ハーフですか?」って声をかけられて、「いや、私たちみんな日本人です」って対応したんですけど……。きっと、この子は大きくなっても英語で話しかけられて、「ナニジンなの?」って聞かれ続けるんだろうなと思います。でも、その答えは周りの人ではなく、あなたが決めることなんだよってことを言い続けたい。
「違う」からこそ、伝えあうことが大事
「子どもたちには、世の中に選択肢も正解もたくさんあることを知ってほしいんです」とナディさん。
以前、映画『ドラえもん のび太の魔界大冒険』を見ていた時に、のび太のママが「ちゃんと勉強していい大学に行かないといい会社に入れませんよ」と話していたんです。勉強が苦手で魔法が使えれば楽になれると思って「もしもボックス」で魔法の国を作ったのに、そこでも勉強しないといい大学に行けず、いい仕事が見つからないと言われていて笑いました。
でも、本当はいろいろな選択肢がある。子どもにはたくさんの選択肢を知って、そのなかから自分は何が好きなのかを学んでほしい。
しかし、いまの社会では「自分は何が好きなのか」「何がしたいのか」を考える機会が少ないことも気がかりのひとつです。
以前、仕事で研修を受けたときに聞いて印象に残った話なのですが、算数が好きな子がいたとしても、成績が悪いと周りから「いや、お前はいつも10点じゃん」って言われますよね。でも、数字を見ていて楽しい気持ちになるとか、自分が算数が好きだと感じているなら、本当はそれでいい。
それなのに、私たちの社会では「算数が好き」「いや、10点じゃん」、「運動が好き」「いや、でも足が遅いじゃん」っていう風に評価して、「好き」を切り捨ててしまう。そうすると自分自身の気持ちよりも、他人の評価に頼るようになってしまいます。
そうじゃなくて、やっぱり「自分がしたいのか」っていう気持ちのほうを、大事にするべきだなって思うんです。だから、子どもたちにも「何が食べたいの?」「どこに行きたいの?」って意見をなるべく聞くようにしています。まあ、私に余裕がなくて希望通りにできないこともあるんですけどね(笑)。
他人の評価ではなく自分は何がしたいのかを大事にして、自分なりの「正解」をもつこと。それと同時に、自分と相手の「正解」は違うという意識をもつことも大事なのだとナディさんは言います。
何が正しいのかは自分で決めればいいこと。でも、自分が思う正しさを人に伝えるときには、相手がどう感じるのかをちゃんと考えて、言葉を選ばないといけないとも思っています。私と相手が違うのは当たり前。お互いに話し合うことも必要です。
普段の生活でも、ナディさんは「相手に聞く」ことを心がけているそうです。
たとえば、子どもや荷物で手いっぱいの状態で、ベビーカーをたたもうとしているお母さんを見かけたら、「手伝いましょうか?」と聞きます。もちろん、なかには「手伝いはいりません」と言う人もいますが、それはそれでいいんです。あと、買い物に行くときには、お向かいに住むおばあちゃんに「何か必要なものがあれば買ってきましょうか?」と声をかけています。そういうちょっとした会話で、いろいろなことが解決できると思うんです。
でも、世の中には「声をかけるのが恥ずかしい」、「嫌がられるかもしれないから話しかけない」という人も多いのではないでしょうか。
そうなんですよね。でも、エスパーではないので、聞いてみないと相手のことは分かりません。みんなそれぞれ考えていることが違うから、うまく察するのは無理です。「分からないし、違うかもしれない」という前提で、いろいろな対話をしていくことが多様性を大事にすることにつながると思うんです。
一昨年、久しぶりにイランを訪れたというナディさん。子どもを連れていると、自然といろいろな人が声をかけて手伝ってくれたことに驚いたと言います。
ショッピングモールで哺乳瓶を落としたら、従業員の人がやってきてウォーターサーバーのお湯できれいに洗ってくれたんです。知らない人でも、みんなが助けてくれました。私はずっと日本が一番豊かな国だと思ってきたのですが、あらためて豊かさって何だろうと考えてしまいました。日本はちょっと忙しすぎるのかもしれません……。
外国人が日本に来て一緒に働くようになると、お互いの違いから気づくことも多いと思うんです。それが「いま、自分たちの社会は暮らしやすいかな」、「働きやすいかな」って考えるきっかけになればいいと思います。
「他人の評価ではなく、自分の気持ちを大事にすること」「正解はひとつではないと知ること」「自分と相手は違うという前提で対話を重ねていくこと」ーーナディさんが自分のアイデンティティを見つけていくなかで大切だと気づいたことは、誰にとっても必要な考え方のように感じます。
「いまでも、まだ悩んでしまうことは多いんですよ」と笑うナディさんですが、最後に「外国の人だけでなく、みんなが生きやすい社会を、一緒につくっていけたらいいですよね。そのためにも自分にできる範囲で体験を共有して、対話していく機会を大事にしたいと思っているんです」と話してくれました。
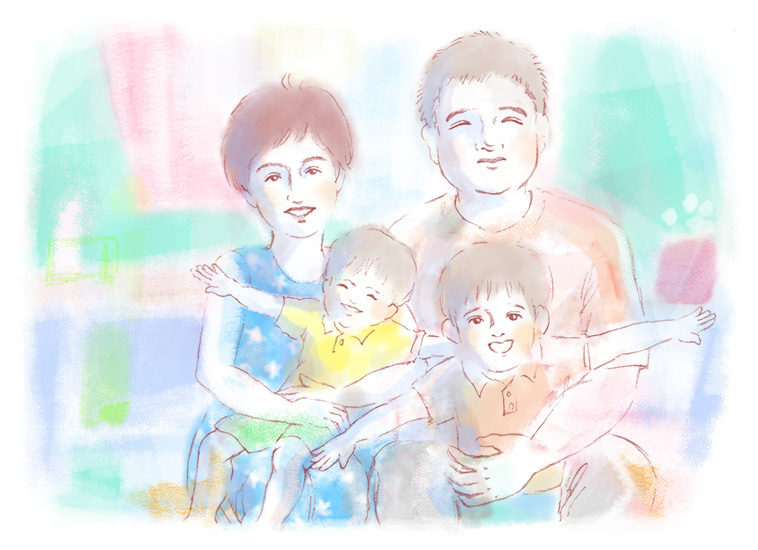
「自分の正解」と同じように「相手の正解」も大事にする
オープンな雰囲気で、どんな質問にも一つ一つ考えながら率直に答えてくれたナディさん。
他者からの評価、そして自分が抱く「こうあるべき」というイメージを乗り越えて自分自身を見つける一番のきっかけとなったのは、さまざまな要素をもつ「自分」を前向きに受け止めていた友人の存在でした。多様なあり方を知り、違いを肯定的に受け止めることで、「自分で正解を決めていいんだ」と気づくことができたのです。そのことは、ナディさんの生き方や人への接し方にも通じているように感じます。
一方で、「つい自分より他人の意見のほうが正しいように思ってしまうことは、いまでもあるんですよ」という素直な言葉にも、とても共感するところがありました。SNSなどでさまざまな意見を目にする機会が増えるなか、他人の目線や評価に流されないことは簡単ではありません。だからこそ、顔の見える範囲での丁寧な対話を大切にしたいのだと話します。
小さい頃からさまざまな経験をしてきたナディさんですが、自分の気持ちを大切にするだけでなく、対話を通じてお互いの違いから新しい視点を得ることにも前向きです。その姿勢から、「自分の正解」を大事にすることは、同じように「相手の正解」を大事にすることでもあるのだと気づきました。
協調性の強い社会のなかでは、「違う」ことが否定的にとらえられたり、不安に結びついたりすることもあります。けれど、もし「世の中にはたくさんの選択肢と正解がある」ということを安心して受け入れ合うことができれば、自分にとっても周りの人にとっても生きやすい、より豊かな関係性が築けるのではないでしょうか。
関連情報:
ナディさん著書『ふるさとって呼んでもいいですか 6歳で「移民」になった私の物語』
(編集/工藤瑞穂、企画・進行/松本綾香・杉田真理奈、イラスト/あさののい)