
家族との間で、仕事のなかで、生きているうちに、いつの間にか澱のように心にたまっていくもの。
日々に紛らわせていると、思わぬ形で心や身体がSOSを出し始め、慌てて立ち止まることになります。これまでに何度か、そんな経験をしてきました。
しかし、生きづらさのような漠然としたものについて、大人になってから誰かと話す機会なんて、ほとんどありません。弱い部分は他人に見せるものではないという見えないルールが、この社会には強くあるように思います。
だからでしょうか。「居場所」だったり、「カウンセリング」だったり、多くの人が安心して心のうちを語れる相手や場を探しているように感じます。もしかしたら語りたくて語れずにいる言葉を、誰もが抱えているのではないでしょうか。
そんなことを思いながら、2018年12月8日に「語り」をテーマで開かれた「soar conference 2018」のセッションを聞いていました。

最初のゲストは、向谷地生良さん(「浦河べてるの家」理事、ソーシャルワーカー、北海道医療大学教授)。トークのテーマは「当事者と語り」です。
soarというメディアが生まれるきっかけにもなったべてるの家では、統合失調症など精神障害のある当事者が、自分自身を研究して病名をつけ、幻聴や妄想について仲間とともに語り合う取り組みを続けてきました。
べてるには、「弱さの情報公開」や「順調に問題だらけ」といったユニークな理念がたくさんありますが、その活動の軸に置かれてきたのは、当事者による「語り」を取り戻すこと。
その取り組みから見えてきた「語りの力」について向谷地さんが語る言葉は、一つひとつが心に染みこむようでした。
精神疾患がある人たちに「語らせてはいけない」
人口約12000人、過疎化が進む北海道浦河町に「べてるの家」はあります。1978年、日赤病院の精神科を退院した人たちを中心に立ち上がった回復者クラブ「どんぐりの会」をルーツに、1984年に障がいのある人と町民有志によって地域活動拠点「べてるの家」が誕生。昆布の産地直送などの事業を起こして自分たちの働く場をつくり、グループホームや共同住宅をもち、診療所など他機関と連携しながら地域での活動を広げてきました。
向谷地さんは、ソーシャルワーカーとして病院に勤務しながら精神科を退院した人たちと地域で生活し、ともにべてるの家を設立しました。

「この約40年間を言い表すとしたら、言葉を取り戻す歴史と歩みだった」と向谷地さんは言います。
それまで精神医療の世界では、精神障がいや精神疾患の人には「語らせてはいけない」と言われていました。とくに統合失調症という病気がある人たちは、幻覚や幻聴などの症状によって、私たちには見えたり、聴こえたりしない世界を経験しています。それを語らせてしまえば、かえって心の闇が開いて具合が悪くなってしまうと考えられていたのです。
向谷地:だから、「聞き出さず、否定も肯定もせずにかわしましょう」というのが精神医療の常識でした。しかし、私には不思議に思うことがありました。たとえばアルコール依存症などの人たちに対しては、精神科医は「これは病院で治すものではない。仲間とのミーティングのなかで治しなさい」と言うわけです。

依存症の場合には「自助グループ」という形で、同じ依存症の仲間たちが集まり、お互いの経験を語り合うことが回復に効果的だとされています。統合失調症の人たちには「語らせてはいけない」一方で、依存症の人たちは、「語ること」「仲間の力」で回復する――向谷地さんは「おかしいな、待てよ?」と考えました。
向谷地:病気にかかわらず、うまく説明しにくい、自分だけでは抱えにくい困難を持ったときには、誰かに聞いてほしいし、わかってほしい。そういう思いを誰もが持つはずです。べてるのみんなに聞いてみても「そうだよ」と言う。そこで、あらためて「語る」ことを大事にしようと考えました。そこから生まれたのが「三度の飯よりミーティング」というべてるの文化なんです。
常識を覆す形で始まった、べてるの活動
「自分自身で、ともに」。これは、べてるで2001年から始まった「当事者研究」の理念のひとつ。当事者研究とは、医師や専門家にすべてを委ねるのではなく、自分自身が「苦労の主人公」として自分の生きづらさを研究し、仲間とともに「自分を助けていく」試みです。べてるでは、こうした当事者研究をはじめ、数多くのミーティングが行われています。
soarのメンバーも訪れた年1回開催されるイベント「幻覚&妄想大会」も、こうしたミーティングでの語りから生まれました。

向谷地:ある日ミーティングをしていると、2階の部屋に住むべてるのメンバーが、「昨日の夜、窓を見たら牛がいて、にらまれた」と言うんですね。それで、「2階からのぞきこむ牛なんているかな」 「牛じゃなくてキリンじゃないか」と、みんなで議論になったんです。
「なんで牛だと思う?」と聞いたら、「牛舎独特のにおいがした」って言う。じゃあ、なんで臭うのかって話になって、彼を問い詰めてみると、実はトイレに行くのが面倒くさくて2階から立ちションしていたことがわかったんです。立ちションのうしろめたさをずっと抱えていたら、突然目の前から牛が現れて、くさい匂いがする息を吹きかけてにらみつけた。うしろめたさが牛になるわけです。すごく面白いですよね。
ほかにも、こんな経験がありました。
向谷地:ひとりのメンバーが「俺の部屋のコメを盗んだだろう」と怒って、突然やって来たこともありました。「どうして私が盗ったとわかるんだ」って聞いたら、「ちょっと部屋に来い」って言う。そしたら三毛猫がいて「この猫に聞いた」って言うんです。
彼が部屋に戻ったときに、誰かが侵入したような気配がした。たまたま米びつを見たらちょっと減っている。誰が侵入したんだって、あいつか?こいつか?向谷地か?って言ったら、「にゃあ」と鳴いたんだ、と(笑)。
べてるには、こんな風に猫と会話ができる人もいれば、カラスやスズメと会話ができる人もいるんです。

しかし、こうした世界に生きている人たちの多くが、「これを語ってはまずいぞ」と自ら口を封じてきました。自分が見ていること、感じていることが、一般には受け入れられないものであることを感じとり、話せば入院させられるかもしれない、どう扱われるかわからないという不安から、自分の経験をあまり語らないようにしてきたのです。
向谷地:ところが、浦河は、そういうことを言っても全然差支えのない世界。そこで、みんなが語り始めるようになりました。北海道の過疎の町で、精神医療の常識を覆す出来事が始まったわけですね。私たちは、ミーティングで彼らと語り合うことが楽しみだったんです。面白いんですよね。おかしみがあるんです。こんなに楽しくて豊かな世界をみんなにも伝えたいと始まったのが「幻覚&妄想大会」でした。
1年間でもっともユニークだった幻覚や幻聴を発表し、さらには表彰までしてしまう「幻覚&妄想大会」。全国から多くの観客が集まる会場は大きな笑い声に包まれます。
医療の場では否定され、語ることも許されてこなかった世界をユーモアを持って共有することは、その存在を肯定することでもあり、生きる力につながります。また、「語り」は自分が抱えている問題から少し距離をおき、客観視するための手段にもなっているのです。
「黒い影の男」を大切な家族として迎えたい

こうして経験が開かれていくことで、「いわゆる『病気』の質も変わってくる」と、向谷地さんは言います。たとえば地方の講演会で出会った、こんな女性がいました。
「会場に(幻聴が)聴こえる体験を持っている方はいらっしゃいますか」と向谷地さんが尋ねると、30歳前後の女性が前に出てきたそうです。彼女はひとりで小学校低学年の子どもを育てているのですが、自分の子どもを蹴ってしまうことに困っていました。
向谷地:「今日、この会場でも聴こえますか?」と聞いたら、その女性は「聴こえます」と言う。それは、のっぺらぼうのような黒い影みたいな存在の男で、会場にいると言うんです。その男との関係を尋ねると「苦労しています」と。
私が「わざわざ、この会場に付き添いのように来てくださっている黒い男に、みなさんまずは拍手しましょう」と言ったら、会場のみんなが拍手をしました。そうしたら女性がびっくりして「黒い男が笑っています。長い付き合いですが、笑っているのは初めて見ました」と言いました。「黒い男が、私に子どもを蹴ろってそそのかすと、私は止まらなくなって子どもを蹴ってしまうんです。実はもう一人、まさこっていう幻聴さんもいて……」
「え、まさこさんもいるんですか。いつからのお付き合いですか」と聞くと「物心ついたときから」だと言います。まさこさんは「もうやめて」って止めるんだけど、やっぱり子どもを蹴ってしまう。「黒い男はなぜ、あなたに大切な子どもを蹴ろって言うのでしょうか?」と言ったら、「私もわからないんです」と。そのときは「じゃあ、一緒に研究しましょう。いずれにせよ、今日は黒い男さんも一緒に来てくれてありがとうございました」と、再び拍手をして終わりました。
後日、その女性から向谷地さんのもとに連絡がありました。彼女は、黒い男に「なんでそんなに私に蹴ろってそそのかすの?」と思い切って聞いたのです。すると「消えたくないの、寂しいの」という声が聴こえてきました。彼女は「この黒い男は、お母さんに甘えたかった私だったんじゃないだろうか」と感じて、その黒い男が愛おしくなり、自分の家族として受け入れたいと思うようになったそうです。

向谷地:オカルトチックな話だと思うかもしれないけれど、これは実際にあった話なんです。こういう経験を、彼女はずっと語れないままに生きてきたんです。
黒い男は「消えたくないの」と言っていました。これはあとで彼女の主治医から聞いたのですが、主治医は大量の投薬をして、この黒い男の声をなんとか消そうとしてきたそうです。けれど、彼女が「この黒い男を大切な家族の一員として受け入れたい」と言ってきたとき、「自分のやり方は間違っていた」と反省したのだと話してくれました。
見えたり、聴こえたりすることは病気ではない

幻覚や幻聴をなくすことが、回復のゴールではありません。べてるでは、自分と違う世界を生きている人を否定せず、それは何か大切な意味を持ったものなのだと受け止めてきました。
「おはよう」という挨拶が「あっち行け」と聞こえる人、「手を洗いましょう」と言っただけで、いじめられていると受け止める人、自分の考えがすべて周りに漏れてしまうと感じる人……べてるではさまざまな世界に生きている人たちが、ともに暮らしています。
向谷地:そういう人たちが一緒に暮らしていくためには、何が必要なのかということを私たちはずっと模索してきたんです。そこで発見したのが、まさに「語ること」でした。
統合失調症のなかには、するどく時代の空気や社会を読みとる能力を持った人たちがいます。そして、それをイメージ化して発信する能力がある。
考えてみたら、アニメの世界では、木が語りかけたり、動物が親しげに話しかけてきたりしますよね。そういう芸術のような世界を描いて、その物語を通して何かを訴えよう、説明しようとする。その世界はまさに統合失調症の人たちが、普段生きている世界なのではないかと、私は思うんです。

向谷地さんが、あるメンバーに「統合失調症ってどういうこと?」と聞くと「五感が幻になる感覚」という答えが返ってきました。五感から伝わってくる世界と、周囲の人たちが共有している世界にギャップがあることで人間関係の摩擦が起きてしまう。そして爆発したり、孤立していったりするのです。
見えたり聴こえたりすること自体は決して病気じゃなくて、それが受け入れられない社会の中で起きるストレスで生きづらくなって「病的」になっているのです。人と違う形で世界を感じることは誰もが少なからずあるし、そういう可能性のある状態の中でみんな暮らしているという風に思うんです。
当事者研究と出会い、自分の世界を語ってもいいのだと知ったメンバーが、「これでやっと生きられる」と向谷地さんに話したそうです。
世界に対して語り返すことの作用
最後に、向谷地さんは2016年7月に起きた神奈川県相模原市の障がい者施設での事件を挙げ、私たちの社会で「語り」が持つ力について触れました。

向谷地:あの事件を起こした青年は、事件直後に「ヒトラーの思想が降りてきた」と話していました。ヒトラーは執拗にプロパガンダを繰り返すことで、国民をマインドコントロールすることに取り組んだのです。そして、70年の時空を超えて、ヒトラーの言葉が青年の思考に降りてきた。
また、この事件と同じ年の3月には、ツイート上の対話から「学ぶ」として公開された人工知能が、ヘイト発言を教え込むユーザーに影響されて、ヒトラー礼賛と差別発言を繰り返すようになったということもありました。これらは同じことだと思うのです。
しかし、私たちはこうしたネガティブな言葉に影響され、世の中にある闇をただ受け入れるだけではなく、それに対して語り返していくこともできます。闇に対して、言葉をもって対抗していく、語り返していく。それは私たちの大切な営みなのではないかと、向谷地さんは考えます。

最初の頃、統合失調症がある人たちは「お前は生きている価値がない。ダメな人間だ」という声にそそのかされます。しかし、べてるで自分の言葉を取り戻し、仲間とのやりとりをしていくうちに、その声が「お前はいいやつだ、よく頑張っているぞ」という風に変わっていくことがあるそうです。それは、つまり「言葉や語りが、私たちの身体のなかに、ちゃんと降りてきている」ということ。
だから、私たちは語ることをあきらめてはいけないのだ、と言います。
向谷地:社会には、もともと汚れた言葉を浄化する作用があったんじゃないかと思います。ひとつの言葉が誰かに伝わり、また誰かに伝わり、そうやって言葉が「人のつながり」という層を経るなかで浄化されていくような機能があったのではないでしょうか。
しかし、いまこの浄化機能が失われてしまい、「汚れた言葉」がそのまま社会に拡散してしまっています。だからこそ、あらためて私たちは、とくにアナログな場で言葉をしっかりと社会に語り返していく必要がある。それは、この病気を経験した人たちから私が学んだ、いちばん大切なことだと思っています。
一人ひとりが自分の「語り」を取り戻す
べてるの人たちが取り戻した「語り」。精神医療の常識を覆した取り組みは、いまでは国内外から大きな注目を集めています。「一度べてるに行くと何度も行きたくなる」と言われるほど、べてるには訪れる人を魅了する力があります。

べてるが目指す「回復」は、人と人とのつながりを回復することであり、自分なりの生き方や対処法を見つけること。「語り」を共有し、そこに仲間がそれぞれの経験や工夫を持ち寄ることで、予想もしない変化が生まれてきました。
本来、私たちはそうやって生きていく力を得てきたのかもしれません。だからこそ、べてるを満たす「語り」に、こんなにも多くの人が惹きつけられるのではないでしょうか。
自分の言葉による「語り」を取り戻すことを必要としているのは、べてるだけではない気がします。わたしも「苦労の主人公」になることを目指してみたいと思うのです。

*********
さて、これで向谷地さんのトークは終了なのですが、当日は会場の参加者から多くの質問が寄せられました。とても印象的なものが多かったので、その一部を要約して最後に紹介したいと思います。

――その人が持っている世界をそのまま肯定するというときに、その語りのなかに自分や周りの人が傷ついてしまう言葉が出てくることもあると思います。それはどのように受け入れたらいいのでしょうか。
向谷地:私は素直に「いやあ、いまの言葉に傷ついたんだけど」って言います。人を傷つける言葉を発しているときは、その言葉をその人自身も聞いているわけです。そういう意味では、その人がいちばん傷ついていて、私は2番目か3番目に傷つく。
「私だったら即死しそうな鋭い言葉に感じたけど、そういう自分に矢をさすような言葉を発しながら、どうやってあなたは生きて来られたんですか。そういう言葉を吐くときのメリットってあるんですか」と、その人にゆっくりお尋ねします。
最近も自傷行為が止まらないメンバーと、そういうやりとりをしていたら、その人がしばらく考えて「そうすることで、自傷行為がしやすくなるかもしれない。そうやって下ごしらえしているんです」。「いや、またそれは大変だね」と。そういう発見があるんですね。なかなか深いですよね。だから正直に言います。こう見えても、私はけっこう傷つきやすいです(笑)。

――以前にべてるの家を訪ねたことがあります。私は病気がよくなってきていて、いまは仕事をもち、人とのかかわりも取り戻せてきているのですが、虚しさが消えません。以前、向谷地さんが「回復すると虚しくなる」と仰っていましたが、それはなぜなのでしょうか?
向谷地:ね、本当にそうですよね。病気の世界でどろどろになって苦労している人たちが回復するときって、夢から覚めたように現実が見えてきます。「あの人が苦手」「こういう場がイヤ」とかが出てきたら、順調な回復だねって言っています。友達ができて、仕事ができて、お金が手に入って、それなりに普通の人のようになったあとには、ちゃんと虚しさが襲って来る。虚しくなったら大成功!みたいな。
精神科医のヴィクトール・E・フランクルが、人が本来持っている空虚とか虚しさをごまかさず、ひとつの大切な可能性の入り口として、そこにちゃんと立てるようになることが治療の目的だというようなことを言っているのですが、私も本当にそうだと思います。宗教も人間の根源にある曖昧さとか不安定さを見つめるところから始まりました。お釈迦さまも、イエスさまも、別にお金に困って始めたわけじゃありません。
べてるでは「苦労が恒久化した」という言い方をするんですが、「病気の苦労」が、生きていれば誰もが抱える「当たり前の苦労」になるということです。答えになっていないかもしれないけれど、仕事を得て、友達をつくり、お金が入るということは、「ちゃんと虚しく」なれるということでもあるんです。よかったですね。

――べてるの「弱さの情報公開」(※)という考え方にすごく救われました。自分もそういう場をつくりたいのですが、無理にではなく、自然と対話が生まれる場はどうやったらできるのでしょうか?
※一人ひとりが自分の抱えている「弱さ」を寄せ合ったとき、人のつながりが生まれ、助け合いがはじまるという理念
向谷地:対話というのは「これから始める」ものではなくて、もうすでに私たちは対話のなかに生きているんです。生まれた瞬間から赤ちゃんは母親と対話をするし、人間の身体は臓器そのものがネットワークをつくって、対等に情報交換しているのだそうです。まさに対話ですよね。そういう対話的環境に最初から生きているということを、まずは知り、意識して活かすことが大事です。
それから、対話っていうのは、必ずしも心地よいものではなくて、こすれ合ったり、ぶつかったり、まさに「対立」のなかでこそ意味を持ってくるもの。
ひとつの例として、べてるで会社をつくろうとなったときですが、最初、メンバーのみんなは「そんなことできるわけない」「自信がない」と言っていました。そうしたら、ある統合失調症の女性が「そうだよね。あなたたちみたいな頭がおかしい人たちが会社をつくってうまくいったら、世の中困らないよね」と言ったんです。それに俄然みんなが怒りまくって、おかげで会社ができてしまった(笑)。
べてるでは、「あんな人とは付き合いたくないな」という人が彗星のように現れて、かき回してカッカしたときに何か思わぬものが生まれてきたという歴史があります。対話は、そういうダイナミズムを持っている。だから、現実のジレンマや行き詰まりがあっても悲観しないで、一つひとつが対話の糸口として可能性が開かれているんだと、やけくそでもいいから心の底で思っているといいと思います。
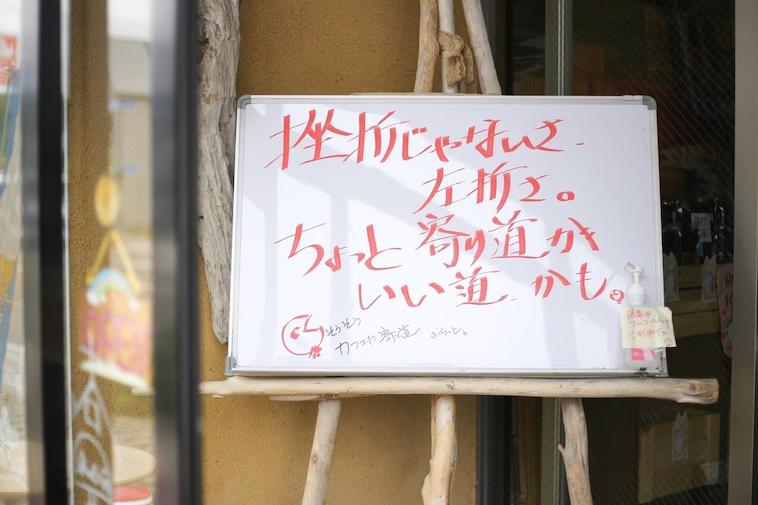
関連情報 べてるの家 ホームページ
(写真/馬場加奈子、協力/山根優花)


