
ぼくの両親は耳が聴こえない。そんな両親を持つ子どもはCODA(Children of Deaf Adults)と呼ばれる。この単語は「聴こえない親を持つ子どもたち」を意味する。つまりは、聴覚障害者に育てられた子どものことだ。
それを知ったとき、ぼくは自分が「マイノリティなのだ」と思った。同時に、幼い頃に感じていた「生きづらさ」は、このマイノリティ性に起因するものなのかもしれない、とも感じた。
世の中にはさまざまなマイノリティ性を持った人たちが存在する。実際、ぼくはsoarの取材を通じて、あらゆる境遇にいる人たちと出会ってきた。耳が聴こえない人、トランスジェンダーの人、学校教育から“ドロップアウト”した人…。
彼らはそれぞれ違いはあれど、なんらかの生きづらさを抱えていたように思う。同時に、彼らは自分らしい生き方を模索し、人生の可能性を広げているようにも見えた。一人ひとりの姿勢の素晴らしさを、いまでもぼくははっきりと覚えている。
そんななか、ぼくはひとつの言葉を知った。「ダブルマイノリティ」という言葉だ。
これはひとつではなく、ふたつのマイノリティ性を持つ人を表すもの。たとえば、セクシュアルマイノリティで精神疾患がある、外国人であり身体障害がある、など。
この言葉を知ったとき、ぼくは率直に、「ひとつのマイノリティ性を持つ人よりも、何倍も生きづらそうだな…」と思ってしまった。
けれど、短絡的にそう考えてしまうのは、とても乱暴なことなのではないだろうか。他者に対し、「生きづらいですよね、大変でしたよね」と思うとき、思考の背景には、対象への“憐憫”が含まれてしまっているような気がする。その行為は、一見寄り添っているようで、相手を見下すことにもつながりかねない。
ぼくはそんなことをしたくない。ならば、ダブルマイノリティの当事者に会って、素直な気持ちを聞いてみたいと思った。
そこで今回お話を聞いたのが、認定NPO法人ReBitの代表を務める藥師実芳(やくしみか)さんだ。

藥師さんは、トランスジェンダー男性(身体的には女性として生まれ性自認が男性であること)とADHD(注意欠如・多動性障害)の当事者であり、現在はLGBTの子ども・若者の課題に取り組み、教育現場での啓発事業やキャリア支援事業を行なっている。その根底にあるのは「LGBTを含めた全ての子どももありのままで大人になれる社会を創る」という想いだ。
LGBTの子どもの現場を変えるには、特に希死念慮が高まる二次性徴期に正しい情報や適切な支援が届く体制づくりが重要であると、教育現場での啓発事業である「教育事業」を行っている。また、就職の際に壁にぶつかってしまうこともあるLGBTの人たちに向けて、セミナーやイベントを開催したり、企業の研修やコンサルテーションを通じた働きやすい職場づくりに取り組む「キャリア事業」を実施。
さらには、LGBTの子どもを含めた全ての子どもがありのままで大人になれる社会の実現には、多様性を包括する社会風土の醸成が重要であるという想いから、LGBTだけに留まらず、他のマイノリティのテーマに取り組む団体と連携し幅広い当事者の人たちをサポートし始めた。
そしてもちろん、そのなかには藥師さん同様に、ダブルマイノリティやトリプルマイノリティの人たちも存在しているそうだ。
当事者として、また同じ悩みを抱える人たちを見つめてきた側として、藥師さんはどんな現実と直面してきたのだろうか。少し緊張しながら尋ねるぼくに対し、藥師さんはやさしく笑いながら口を開いた。
トランスジェンダーであることを自覚して、自殺未遂までした青春時代
――まずは幼少期に自分のセクシュアリティ(性のあり方)をどう捉えていたのか教えてください。
藥師さん:幼い頃から、自分のことを女の子だとは思っていなかったんです。アメリカに住んでいた小学2年生の頃、女の子を好きになって。でも、それがおかしいとは思わなかったんですね。そもそもユニークであること、人と違うことを尊重するようなカルチャーがあったので、クラスの子たちに「女の子が好きなんだ」と打ち明けても否定されることがなかった。
――当時のアメリカ自体が多様性を重んじる風潮だったんですか?
藥師さん:アメリカ全土を語ることはできないですが、少なくとも私が通っていた学校ではそういうカルチャーが広がっていました。生徒たちの人種やバックグラウンドが多様で、一人ひとりがちがうということが当たり前だったように感じます。ジーパンにスニーカーを履いて、パーカーを合わせる、みたいな服装でしたが女の子らしくしなさいと言われたことはなかったですね。

――その後、小学4年生で日本に帰国して、環境は変わりましたか?
藥師さん:先生たちから「女の子らしくしなさい」と言われました。
――そこで「らしくあるべき」問題に直面したんですね。
藥師さん:そう。でも、いま考えると、先生にも悪気があったわけじゃなかったんだろうなとも思うんです。日本語があまり喋れなかったので、早く友達ができるように”同性の”女の子と仲良くしなさい、という意味で言っていたのかなと。
とはいえ、私は自分のことを女の子だとは思っていなかったので、違和感がありました。あぐらをかいて座っていると「女の子なんだから」とたしなめられて、バレンタインになると周囲の女の子たちが男の子にあげるチョコの話題で盛り上がっていてその輪に入れない。「女の子」として「女の子だと思っていないのに」と性別違和を感じていました。
――そこから、いつ「トランスジェンダー」であることを自覚したんですか?
藥師さん:小学6年生の頃に放送されていたドラマ『3年B組金八先生』を観たのがきっかけです。上戸彩さんが性同一性障害の役を演じていて(2001年10月から2002年3月放送の第6シリーズ)、「あ、自分はこれなんだ」と思いました。
――覚えています!あのドラマで、世間に「トランスジェンダー」が広まりましたよね。それをきっかけにご自身のセクシュアリティがはっきりして、すっきりしましたか…?
藥師さん:うーん…。当時はトランスジェンダーに関する情報って、ネガティブなものが多かったんです。たとえば、「ホルモン投与をすると30歳で死んでしまう」とか、「日本では働けない」とか。調べれば調べるほど、「そうか、私はありのままでは生きていけないんだ」と絶望しました。だから、必死で隠すようになって、女の子らしくしようと頑張ったんです。

――自分のセクシュアリティが判明したことにより、当時の間違った情報にも触れることになり、結果としてつらくなってしまったんですね…。
藥師:そうですね。それでも我慢し続けた結果、高校2年生のときに「もう無理だ」と爆発してしまって…。神奈川から東京まで電車通学していたんですけど、帰宅する途中で電車に飛び込もうとしたんです。
――そんなに追い詰められていたんですか…。
藥師さん:本当の自分を押し殺して、クラスでも明るく楽しい子を演じていたんです。バレたら終わりだと思っていましたから。
――相談できる人もいなかった?
藥師さん:当時はいないと思いこんでいました。でも、いよいよ生きていけないとなって、思い切って打ち明けてみたんです。初めてカミングアウトしたときのことは、いまでも覚えています。校庭にあるハナミズキの木の下に友達を呼び出して、トランスジェンダーであることを話したんです。そうしたら、「藥師は藥師なんだから、別にいいんじゃないの」って受け止めてくれて。そこから少しずつカミングアウトするようになっていきましたね。
ADHDも発覚――ダブルマイノリティであることを知った
――トランスジェンダーであることがわかったときのことを話していただきましたが、次にADHDであることがわかったときのこともお聞きしたいです。
藥師さん:振り返ってみると、幼い頃から大変なことばかりだったんです。たとえば、友達から借りたマンガをキレイな状態で返せたことがない。かばんのなかでぐちゃぐちゃになっていたり、なくしてしまったりして、結果、友達との関係も悪くなる、ということがしょっちゅうありました。そのたび、どうして「借りたものをきちんと返す」ということができないんだろうと悩みましたね。

大学に通っていた頃も、内定が決まっているにも拘わらず、卒業までの単位が足りていないことが判明したり。自分では何度も計算したつもりだったのですが、直前まで気がつかなかったんです。
――それで自分はADHDなのではないかと疑いはじめた?
藥師さん:いや、それも偶然で。ADHDだとわかったのはつい最近、3年くらい前のことなんです。男性ホルモン投与のために通っていた病院の先生が発達障害の専門医でもあって、「(トランスジェンダー以外に)なにか気になることはある?」と尋ねられたときに、「多動性みたいなところがあるんです」と相談してみたら、発達障害を調べる問診を受けることになって。その結果、ADHDだとわかったんですよ。
ダブルマイノリティにはどんな生きづらさがあるのか
――トランスジェンダーとADHDのダブルマイノリティだということがわかったわけですね。そこでお聞きしたいんですが、ダブルマイノリティであることで、生きづらさは複雑化したんでしょうか?
藥師さん:そうですね…。ふたつのマイノリティ性についての知識がない人からは、とても誤解されやすいかもしれません。以前、トランスジェンダーであることとADHDであることを同時に伝えたときに、「発達障害があるから性別がわからないの?」と訊かれたことがあって。
――それって関係ないんじゃ…。
藥師さん:そう。そもそもトランスジェンダーは性別がわからない状態ではないですし、私にADHD特性があることと、身体の性と性自認が異なることは別の話です。それが別の話であることを一つひとつ説明することはできるんですけど、説明が複雑化しやすいですし、聞き手も混同しがちでとても大変なんですよね。
同時に、マイノリティ当事者のコミュニティのなかでも疎外感があるとも思いました。たとえばセクシュアリティや障害など、特定のマイノリティ性でつながっているコミュニティだと他のマイノリティ性への理解があるのではと思われることもありますが、必ずしもそうとは限らない。他のバックグラウンドを持つ人が想定されていないことで、なんとなく居づらかったり、適切なサポートを受けられないこともあります。
――同じマイノリティ性でつながっているのに?
藥師さん:もっと噛み砕いていうと、たとえばトランスジェンダーのコミュニティではヘテロ(異性愛)であることが前提として語られ、トランスジェンダーでかつゲイやレズビアンであると伝えると、疎外感を感じることもあります。
また、トランスジェンダーで精神疾患がある人もその場にいるということが想定されていないと、精神疾患を揶揄するような発言がされることもありますよね。複数のマイノリティ性を持つ人がいることが想定されていないと、疎外感やハラスメントが生まれてしまう可能性が高まるんです。

――ただ、自身の持つ特徴のすべてが誰かと合致する人はいないようにも感じます。
藥師さん:おっしゃるとおりだと思います。でも、マイノリティ性がかけ算されていくと、より困難が生じやすいんです。ダブルマイノリティやトリプルマイノリティの人たちは、まだ社会的に想定されていないことも多くて。そういった人たちが特定のマイノリティの支援をしているところにアプローチしても、適切な支援を受けられなかったり、たらい回しにされることもあります。
一方で私たちもLGBTのキャリア支援をする中で、ダブルマイノリティ・トリプルマイノリティ性を持つ人たちのサポートを多くさせていただいていますが、一団体での支援の難しさを感じています。だからこそ、特定のマイノリティ分野に取り組む各団体が連携することが大事であると身をもって感じています。
――そのなかで、藥師さんがダブルマイノリティを開示しているのはどうしてですか?
藥師さん:大きくわけるとふたつ理由があるんです。ひとつは、いまの私自身仕事をする上で、どうしても苦手なことがあります。たとえば、紙書類の管理が苦手で無くしてしまいやすかったりするのですが、先方に「自分たちを蔑ろにしているの?」と誤解を与えてしまうリスクがあります。
しかし、自分の特性を伝えた上で「できれば書類はPDFでいただけないでしょうか」とお願いすると、私自身仕事がしやすくなりますし、誤解を与えてしまうリスクも下がると感じています。
そしてもうひとつは、ReBit職員・メンバーの心理的安全や開示しやすさにつながればという願いからです。さまざまな特性を持つ職員・メンバーがあわせて600人いるので、代表である私自身が開示をすることで、携わるみんなが必要に応じて自分のことを打ち明けやすくなればいいなと。
誰もが得意・不得意なことや、仕事をする上であると嬉しいサポートのされ方があるので、それを開示しあうことにより、チームの心理的安全性が上がりますし、チームとしてのアウトプットも高まると感じています。
一人ひとりの属性は、多層的で交差している
――一人ひとりが様々な特性や属性を持ち合わせているんだ、という考え方はReBitの事業にも根付いているように感じました。
藥師さん:そうですね。「インターセクショナリティ」について自覚的でありたいと考えています。

――それはどんなものですか?
藥師さん:インターセクショナリティとは、人種や国籍、性的指向・性自認、障害など、一人ひとりの属性は多層的で交差している、という考え方です。それにより、困難性や差別構造が多層化していると言われています。
そして、国際的にも、ダブルマイノリティやトリプルマイノリティの人たちへのサポートの必要性やその難しさが議論されています。それぞれが多層的で交差しているからこそ、必要な支援が一般化しづらいんです。
トランスジェンダーで発達障害がある人、トランスジェンダーでHIVである人、トランスジェンダーで低所得の人と、一人ひとり対応の仕方が異なるため、包括しづらい。
さらにいうと、就労支援上の問題もあります。トランスジェンダーで発達障害のある人が就職しようと思ったとき、企業側にはそのふたつのマイノリティ性への理解が求められる。でも、大抵は「トランスジェンダーの人は初めてなんです」「その上で発達障害をもっていると難しいのでは」となってしまうんですよ。
それは私たちのような支援や啓発をする団体らが連携することで改善できることもあると考えています。
複数のマイノリティ性を持つ子どもたちもありのままで大人になれる社会にしたい
――続けて、藥師さんがいまの活動をするに至った経緯もお聞きしたいです。
藥師さん:大きなきっかけは、大学生時代に出会ったひとりの先輩ですね。私、大学入学と同時に周囲にカミングアウトをして、トランスジェンダー男性として生きるようになったんです。そこで入ったのが、社会課題をイベントにするというサークルでした。
で、1年生の頃に「LGBTについて取り上げたい」と提案したんです。そうしたら、幹事長だった先輩が「よし、LGBTのイベントをやろう」と言ってくれて。
――その先輩が、きっかけとなった人物ですか?
藥師さん:そうです。その人はずっと柔道部で育ってきたような男性で、「なよなよしている男が嫌い」というような人でした。
でも、私がカミングアウトしたときに、「俺はLGBTとか分からないし、実際に出会った当事者はお前が初めてだし、よくわからん。でも、もしもこれから俺が失礼なことを言ったら、全部指摘してくれ。できるだけ直すし、それでも変わっていなかったらまた指摘してくれ」って言ってくれたんです。

――そこまで言えるのって、素晴らしいですね。自分の無知な部分を指摘してほしいって、なかなか言えることではないと思います。
藥師さん:ですよね。だから私も先輩を信頼できたんだと思います。先輩はいまもReBitの理事を務めていて、ずっとアライ(LGBTを理解し支援する立場の人たち)なんです。あれから12年お世話になっていますが、セクシュアリティの事に限らず互いに気になることを言われたら、指摘しあえる関係であることはありがたいなと思っています。
おかげで、「LGBTでない人はどうせLGBTのことはわからないだろう」と思うことはなくなりました。
――まるで恩人のような存在ですね。
藥師さん:本人には絶対に言わないですけど、本当に感謝しています。たったひとりの存在が誰かのセーフスペースになることを知りましたし、聞こう・知ろうとしてくれるその姿勢と繰り返しの対話で互いのちがいについて理解しあえる部分も多いのだなと学びました。
――そのサークルで開催したイベントをきっかけにReBitが生まれたわけですか?
藥師:そう。イベント後に先輩から「たった一回で終わるのはもったいない。おまえの本気はそんなもんか?」と言われて、ReBitの原型となるサークルを立ち上げたんです。でも、大学を卒業する頃にはReBitを仕事にするということは、考えていなくて。内定をいただいた広告系の会社に就職したんです。
ただ、しばらくすると、並行して運営していたReBitでの受注案件がありがたいことに増えていって、いよいよ学生団体では回しきれないという状況になったんです。そこで当時の代表から「ReBitに戻ってこないか」と打診があったこと、また自分自身がやっぱりLGBTの子どものことに携わり続けたかったこともあり、会社を辞めてReBitをNPO法人にしました。
――NPO法人化をきっかけに、キャリア事業がスタートしたんですね。
藥師さん:そうですね。就活を経て社会人になり、キャリア形成への課題感を身をもって体験したことが大きいです。振り返れば、小学生の頃から、「トランスジェンダーである自分は就職できないのではないか」と不安に思っていました。
また、私が就活するときにはロールモデルも少なく、相談できる人もいなかった。面接官に差別的な言動を受けても一人で抱え込むしかない、というようにしんどい経験をしました。そのような状況の中で「男として働けるんだったらなんでもいいや」と、自身のキャリアに向き合う機会を持てませんでした。
調査によると、トランスジェンダーの希死念慮の第二のピークは、思春期に続いて社会に出るタイミングであるといいます。それまでは学齢期の啓発やサポートをすれば「ありのままで大人になれる」と思っていたのですが、そんな現実があるならば、キャリア初期のサポートも必要であると、ReBit事業拡大をしてキャリア支援をはじめることにしました。
具体的に行なっているのは、就活生らのキャリア支援と企業研修、就労支援者へのサポートです。それと学校等の教育現場でのLGBTについて授業・研修や教材作りといった、教育事業も行なっています。加えて、各地域のLGBTの若者のリーダーシップ育成を行う事業にも取り組んでいますね。

――それともうひとつ、「RAINBOW CROSSING TOKYO」というイベントも行なっていますよね。
藥師さん:これは2016年から開催しているキャリアフォーラムなんです。昨年は10月に渋谷で開催して、36の企業と1000人の学生や社会人の方に参加してもらいました。
2016年からの3年間は「LGBTも自分らしく働けるように」というのを目的に、あくまでもLGBTにフォーカスしたイベントとして運営していましたが、2019年からはLGBTに加えて、ジェンダー、エスニシティ、障害という4つのテーマを掲げています。
厚労省、文科省、東京都、経団連などから後援をいただいていて、官民産学連携のなかでダイバーシティやインクルージョンを考えるプラットフォームとして機能していますね。
――実際にどんな人たちが参加しているんですか?
藥師さん:事前に「自分にはどんな特性がありますか?」というアンケートに答えてもらったんですけど、85%の人がなにかしらのマイノリティ性があって、42%の人がふたつ以上のマイノリティ性があると回答していました。
ダブルマイノリティ、トリプルマイノリティであることを安心して言える場所は多くないので、それを開示しても大丈夫なんだと思ってもらえたことは、うれしかったですね。
――ダブルマイノリティ、トリプルマイノリティの人たちは、どんなことで悩み、RAINBOW CROSSING TOKYOに参加したんでしょうか?
藥師さん:複合的なマイノリティ性を持っている場合、「自分は働けないんじゃないか」もしくは「キャリアにおける選択肢が圧倒的に少ないのでは」と不安に思う人は少なくありません。
でも、イベントに参加してみて、ダイバーシティ&インクルージョンに横断的に取り組む企業を目の当たりにしたことで、自分らしく働けるんだという希望を持ちましたとの声ももらえました。そんな声を聞くと、ReBitをやっていてよかったと思います。
特性やバックグラウンドで選択肢が狭まってほしくない
――ReBitとして就労支援や教育現場に携わってきて、社会が変わったという実感はありますか?
藥師さん:ありますね。それこそ、団体をはじめた2009年当初は、LGBTという言葉を知らない人がほとんどでしたし、大手メディアの記者さんに「ゲイなんて性的な言葉は掲載できない」と言われることもありました。
節目となったのは、2015年に渋谷区と世田谷区が同性パートナーシップ制度を開始したことだと感じます。行政が動いたことで、メディアでも広く報じられました。それに伴い、企業側も「もし社員が同性パートナーシップ証を結んだ場合、法律上の家族に限定している福利厚生はどうしたらいいんだろう」など社内での検討が始まるきっかけとなった。
他の自治体も、「うちの自治体にもLGBTの人たちはいる、なにをすべきだろう」と議論が深まるきっかけになったと感じます。
そして、2014年にオリンピック憲章に性的指向による差別禁止が明記されたこともあり、2020年のオリンピックに向けて、日本全体でLGBTの話題を多く取り上げていただけるようになり、取り組みが促進してきているように思います。

――なるほど。一方で、もっと身近な部分での変化は感じますか?たとえば、昔みたいに「同性愛なんて気持ち悪い」と言ってしまうような人たちが減ったとか…。
藥師さん:そこはまだ課題があるように思います。ただ、LGBTという言葉の認知度が上がっているのは事実。2019年からは中学校の教科書の一部にLGBTについて載るようになって、今年からは小学校の教科書の一部にも載ることになっているんです。
アニメで男の子同士が手をつなぐ描写がされていたり、LGBTを題材にした絵本や児童書も増えていたり、そういったドラマも放送されたりと、メディアのなかでの描かれ方に変化が訪れたことも認知されるようになった一因でしょうし。ただし、「まさか自分の身近な人はLGBTでないだろう」というアンコンシャスバイアスはまだあると感じています。
――藥師さんはLGBTだけではなく、すべての人が自分らしく生きられる世の中を目指しているんですね。
藥師さん:そうです。すべての子どもが属性・特性にかかわからず自分らしいと思う選択肢を選べたらいいなと思います。
たとえば、男の子が魔女っ子のアニメを観たっていいし、女の子がパイロットを目指したっていいじゃないですか。とはいえ、男の子らしい男の子、女の子らしい女の子を否定しているわけでもない。
それはそれで素敵ですし、でもそこだけにとらわれず、多様な選択肢から自分らしい選択が選べることで、すべての子どもの可能性が広がるのではと思っているんです。
その子の選択肢がジェンダーやバックグラウンド、特性で狭まらない社会になってほしいなと。

――そのなかにはダブルマイノリティやトリプルマイノリティの人たちも含まれるわけですよね。そんな人たちに向けて、伝えたいことはありますか?
藥師さん:あなた自身が唯一無二で素敵な存在なんだよ、ということをまずは知ってもらいたい。あなたに対して社会が勝手にタグ付けをしたりとか、いろんな名前を付けたりもするんだけど、やっぱり自分自身のアイデンティティを決めるのは自分なんです。
そして、特性や属性、バックグラウンドによって、自分には選択肢がないんじゃないかと思ってしまうこともあるかもしれないのですが、実はすでに取り組んでいる支援者、企業、行政サービス等があるかもしれない。だから、情報にアクセスしてもらいたいですし、私たちも連携し合いながら必要な人がより情報を得られるよう取り組みたい思っています。
それと、これは私が言われたことなんですけど、「誰もが生きているだけで、誰かのロールモデル」。あなたが生きていることが、次世代の誰かをハッピーにすることにつながる可能性があるんです。だからこそ、自分のために生きてほしいですし、自分のためにハッピーであってほしいと思います。
誰もが生きているだけで、誰かのロールモデルになれる
藥師さんのお話を伺って、やはりダブルマイノリティであることによって、ぼくらがなかなか想像できない生きづらさを感じている人もいると知った。けれど、それは彼らが人一倍苦難な道を歩まなければいけない、ということではない。
複数のマイノリティ性に悩む人も、ひとつのマイノリティ性で苦しんでいる人も、あるいはマジョリティとして生きている人も、一緒。LGBTであることで苦労している人がいる一方で、そうではないとしても、「男らしさ」や「女らしさ」というバイアスに苦しめられている人もいる。
きっと、いまの世の中は誰もがなにかしらの生きづらさを感じているのだ。けれど、それを悲観する必要はないとも思った。
それはつまり、誰もが他人の痛みを理解することができるということだから。そして、人は痛みを共有することで、手を取り合うことができるはずなのだ。
その先にあるのは、藥師さんが言っていたような「誰もが唯一無二で素敵な存在」だと認められる社会なのだろう。そんな未来が早く訪れるといいな。そう思いながら、私は帰り道で藥師さんの言葉を何度も反芻していた。誰もが生きているだけで、誰かのロールモデルなのだ――。
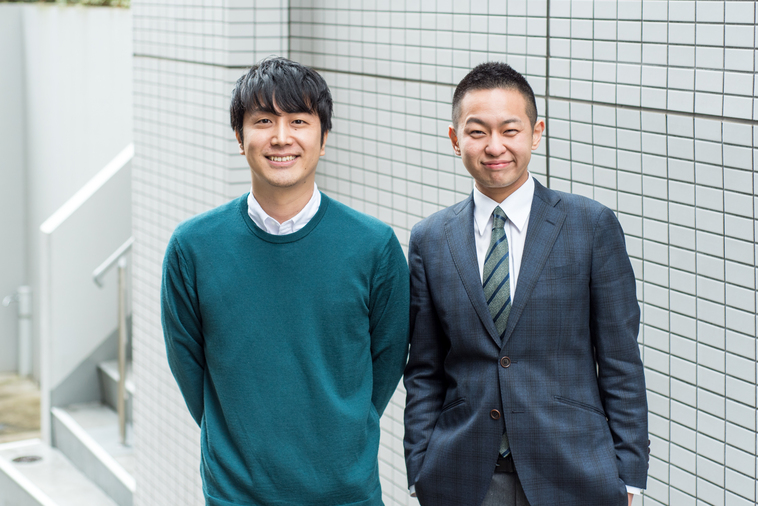
関連情報:
ReBitウェブサイト
(写真/川島彩水、編集/soar編集部、企画・進行/佐藤みちたけ)



