
本来なら、うれしい出来事であるはずの妊娠・出産。けれど、さまざまな事情から産むことや育てることに不安を抱える女性が多くいます。
国の報告によると、児童の虐待死が多い年齢は0歳児、しかも生後1か月に満たない赤ちゃんです。その理由には「思いがけない妊娠」があげられています。そこまで追い詰められる前に、助けを求める先はなかったのでしょうか。
今回、私たちは、熊本県の病院内にある「こうのとりのゆりかご」の開設にかかわった方のもとを訪れました。「こうのとりのゆりかご」は、日本で唯一、匿名でも赤ちゃんを預けることができる場所として知られています。
しかし、お話を伺ってみて、実はこの取り組みがもっとも大事にしてきたのは「相談」なのだと気づきました。そこで感じたのは、誰にも頼ることのできない女性の「最後のセーフティネット」をつくり、子どもの命をつなぎたいという思いです。
匿名で赤ちゃんを預ける「こうのとりのゆりかご」
熊本県熊本市にある「医療法人聖粒会 慈恵病院」に「こうのとりのゆりかご」が開設されたのは、いまから10年前。TVや新聞などで使われてきた「赤ちゃんポスト」という言葉のほうが聞きなじみがあるという人は多いかもしれません。

本来の役割は「新生児相談室」なんですよ。事情を抱えたお母さんには、まず相談してほしい。でも、どうしても相談できないという場合に、命を守るために匿名でも赤ちゃんを預けることができる場所。いちばん大事にしているのは「相談」なんです。
そう話すのは、「こうのとりのゆりかご」の開設準備からかかわった、慈恵病院の元看護部長・田尻由貴子さんです。2015年に65歳で慈恵病院を退職し、現在は「一般社団法人スタディライフ熊本」の24時間相談窓口で、妊娠・子育ての電話相談を受けています。
その笑顔からもあたたかい人柄が伝わってくる田尻さんは、これまで数多くの女性から妊娠や出産に関する相談を受けてきました。「こうのとりのゆりかご」での8年間の経験を通じて、どんな現状が見えてきたのでしょうか。
その場に母親が立ちすくんでいることも…
「こうのとりのゆりかご」は、熊本駅から車で10分ほどのところにある慈恵病院の敷地の片隅にあります。
赤ちゃんを抱えていても開けやすいように工夫された門を入っていくと、そこには「赤ちゃんを預けようとしている方へ まずはご相談ください 秘密は守ります」と大きく書かれた看板があります。
室内の保育器(ベッド)へとつながる外扉の横には、相談用のインターフォンがあり、持ち帰ることのできる相談先のカードも置かれています。その外扉を開けると、「お母さんへ」と書かれた手紙が置かれていて、手紙をとらなければ内側の扉を開けることができません。
こうして、何重にも相談を促す仕組みになっていることがわかります。
赤ちゃんが保育器に置かれると、センサーで知らせを受けたスタッフが新生児室とナースステーションから駆けつけて、赤ちゃんの安全とそこにとどまっている人がいないかを確認します。

預けに来た人が、その場に立ちすくんでいることもあるんですよ。出産直後はパニックになって預けに来たけれど、あとから冷静になって病院に連絡をくれることもありました。預けにくるのはお母さんだけでなく、パートナーやお母さんの親だということもあります。
内扉に置かれた病院からの手紙は、あとからお母さんが名乗りでるときに手がかりになるようにと考えられたものです。
インターフォンを目立つ位置に変えたり、手紙をとらないと内扉が開かないようにしたり、仕組みは運用しながら少しずつ変えていきました。なんとか相談につなげたい、せめて子どもがル―ツをたどることができるようにしたい、と思ってきたのです。
「こうのとりのゆりかご」には、これまでに130人の赤ちゃんが預けられてきましたが、預ける前に相談へとつながった人たちもいます。そして預けられた赤ちゃんは、8割以上の身元が判明しているのだそうです。
ドイツでの視察と、赤ちゃんの遺棄事件
田尻さんが慈恵病院の看護部長に就任したのは、2000年のこと。2002年からは、年1~2週間ほどの期間限定で病院に24時間の電話相談窓口を設け、思いがけない妊娠や育児に悩むお母さんたちの相談を受ける取り組みを始めます。
「こうのとりのゆりかご」を開設するきっかけとなったのは、妊婦と胎児の命や尊厳について考える民間団体「生命尊重センター」の誘いを受けて、2004年に慈恵病院の理事長・蓮田太二さんといっしょに参加したドイツへの視察でした。

ドイツでは、赤ちゃんが森やごみ箱などに遺棄されて亡くなることに心を痛めたお母さんたちが、2000年に保育園の一角にあたたかいベッドを置きました。それが「こうのとりのゆりかご」のモデルになった「ベビークラッペ」の始まりです。2004年に視察で訪れた当時、ドイツ国内の70ヶ所にベビークラッペがありました。
田尻さんたちがドイツに視察で訪れた時点では、これを日本につくろうとは考えていなかったそうです。
帰国して2005~2006年の間に、赤ちゃんの遺棄事件が3件も起きたんです。ドイツの取り組みを見たあとだから、そうしたニュースがどうしても目に留まる。理事長も私も、遺棄される前に出来ることがあるんじゃないかと考えるようになりました。
理事長の蓮田さんも田尻さんも、「とにかく赤ちゃんの命を救いたい」の一心だったと話します。
しかし、「こうのとりのゆりかご」の構想を発表すると、世の中からは大きな反響があり、さまざまな疑問や批判の声があがりました。
新聞には大きく「赤ちゃんポスト」と書かれていました。私たちがつけた名称ではないのですが、いまもそれが一般に広がっています。病院の電話は鳴りっぱなし、マスコミも駆けつけて、蜂の巣をつついたような騒ぎになりました。相談につなげる仕組みよりも、どうしても匿名で預かるところばかりが取り上げられましたね。
「こうのとりのゆりかご」をめぐる議論
とくに議論になったのは、「育児放棄を助長する」「子どもの出自を知る権利が守れない」という2つでした。
いまも、この議論は続いています。「親が子を捨てるのは許せない」というのは、多くの人がもつ考えでしょう。でも、それまでの電話相談の経験からも、思いがけない妊娠をした女性たちの切迫した状況をみてきました。「こうのとりのゆりかご」をつくったのは、何より赤ちゃんの命を優先したいと思ったからです。

「子どもが自分の出自を知る権利」については、田尻さん自身も複雑な思いを抱えています。
思いがけない妊娠をした女性は「誰にも知られたくない」と思っています。匿名だからこそ、最後のセーフティネットである「こうのとりのゆりかご」にたどり着く人もいる。それでも、可能なかぎり出自を知る権利を担保したいという強い思いが、私自身にもあります。匿名にすることで入り口のハードルを下げて、そこから実名での相談につなげられるのがいちばん望ましい。
赤ちゃんを預けに来る理由は、生活の困窮だったり、未婚や若年での妊娠だったりとさまざまです。
結婚の約束をしていたのに出産前に相手がお金を持って逃げてしまったという人もいれば、妊娠を親に言えないまま出産した中学生や高校生もいました。また、出生前検診で十分な説明もないまま胎児の障害を告げられて、うつ状態になっていた女性もいます。
事情はさまざまですが、誰にも言えずに、ひとりで悩んで苦しんで、最後の手段として「こうのとりのゆりかご」に預けに来るんです。
産む前に、頼れる相談先があれば…
「こうのとりのゆりかご」の利用者は、熊本県だけでなく全国からやって来ます。預けられた130人のうち62人が、医師や専門家の立ち会わない無介助出産(孤立出産)だったことも分かっています。
そうやって一人で出産する前に頼れる相談先がなかったということが、いちばん大きな問題ではないでしょうか。だからこそ、私は病院を退職したいまも、妊娠にかかわる相談にかかわっているのです。
慈恵病院では「こうのとりのゆりかご」の設置と同時に、「SOS赤ちゃんとお母さんの相談窓口」(SOS電話)という、フリーダイヤルで匿名可能な24時間相談窓口を常設しました。
「こうのとりのゆりかご」に預けられる赤ちゃんの人数は開設2年目をピークに減少しましたが、SOS電話への相談件数は年々増えています。田尻さんも病院を退職するまで、このSOS電話で相談を受けてきました。
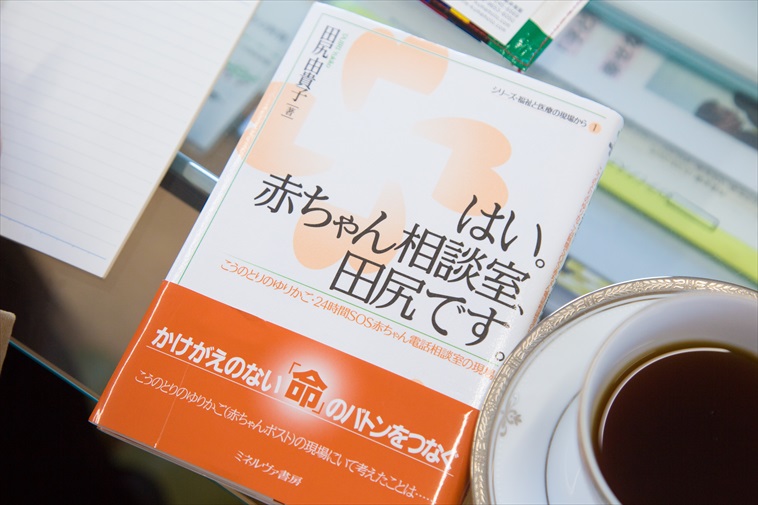
いちばん多いのは「妊娠したかもしれない」という不安の電話。それから、思いがけない妊娠がわかってからの相談でした。妊娠しても、家族にもパートナーにも友達にも言えないから電話をかけてくる。その相談をしてくれた人をしっかりと支えないといけない。なぜなら、こうした人たちが「こうのとりのゆりかご」の利用者になるかもしれないから。
田尻さんが大事にしてきたのは「相談を受けたときに相手を責めない」ということ。「少なくとも自分だけには本音を話せるように」と耳を傾けてきました。
育ってきた家庭や環境に問題を抱えている場合もあり、それぞれに複雑な事情があります。行政の相談窓口で「家族で解決してください」と言われたり、「産んでから相談に来てください」と突き放されたりした経験がある人もいました。
「命のバトン」をつないでいきたい
「もし相談の電話を途中で切られたら、一人で産んで赤ちゃんを遺棄してしまうかもしれない」――田尻さんは、そんな危機感をもって電話を受けてきたと話します。
当時は、相談優先でほかの仕事はあとまわし。昼も夜もなく、会える場所だったら駆けつけました。いま講演で全国をまわっていますが、「あのときに相談した者です」と会いに来てくれることもあるんですよ。中絶しようとしていた人が相談することで思い直して、自分で育てることになったときがいちばんうれしい。どうしても育てられない事情があるときは、特別養子縁組というかたちで命をつないできました。
相談者に寄り添いながら、田尻さんは、その人が本当はどうしたいのか、生んで育てたいのか、育てられないと感じているのかを聞いていきます。
もし「何らかの支援があれば自分で育てられる」とわかった場合には、住んでいる地域の行政や民間の支援先などから信頼できるところを探してつなぎます。
また、自分で育てることが難しい場合には、病院で安全に出産してもらい、生まれた赤ちゃんが家庭のなかで育てられるようにと特別養子縁組へとつないできました。田尻さんが在籍していた8年の間に、実に235人の赤ちゃんの特別養子縁組が成立しています。

赤ちゃんは、できるだけ早いうちから家庭的な環境のなかで育てたほうがいい。世の中には、血のつながりがなくても精いっぱいの愛情を注いで育ててくれる人がいます。産む人から育てる人へと、命のバトンをつないでいけたらいいのではないでしょうか。
ドイツの充実した支援と日本の現状
ドイツをモデルに始めた「こうのとりのゆりかご」ですが、その運営には大きな違いがあります。
日本では、「こうのとりのゆりかご」に赤ちゃんが預けられると、まず警察と児童相談所に連絡をします。そこで事件性がないとわかれば、児童相談所の判断で要保護児童として保護されます。もし産みの親が名乗りでなければ、市長が名付け親となって戸籍がつくられ、その後は乳児院へと移されます。
一方、ドイツで「ベビークラッペ」に預けられた赤ちゃんは、保護されたあとはボランティアの里親のもとで8週間まで育てられます。8週間が経った時点で、産みの親が名乗り出てこない場合には、すみやかに養子縁組が進められるのです。
「こうのとりのゆりかご」は赤ちゃんを預かる窓口だけで、保護されたあとは介入ができません。また、少しずつ状況は変わってきていますが、日本では特別養子縁組の制度自体があまり浸透していないのです。
さらに、ドイツには妊娠や子育てについての相談を受ける「妊娠葛藤相談所」が全国に約1600ヶ所あり、自分の名前を明かさなくても出産できる「匿名出産」や「内密出産」の制度もあります。
2014年から実施されている「内密出産」では、相談機関には実名を明かしますが、匿名のままで出産が可能です。お母さんは安全な施設で出産することができ、子どもは将来、生みの親を知ることができるので、出自を知る権利も守られるのです。
慈恵病院でも、この「内密出産」制度の導入を検討していますが、法整備や費用負担など、まだまだクリアしなくてはいけないハードルがあります。

ドイツのように、出産前後の伴走的なサポートまで実現できたらいい。こうした手厚い支援制度の背景には、ドイツ基本法に胎児の尊厳が明記されていることがあると思います。日本とドイツの大きな違いですよね。
ドイツの「ベビークラッペ」は、思いがけない妊娠・出産にかかわる問題の「シンボル」であり、また社会全体が生まれてくるかけがえのない命を大切にしようとしていることの「シンボル」でもあると田尻さんは考えます。
日本でも「こうのとりのゆりかご」がシンボルとなって、出産前後の女性への支援を充実させていくことで、匿名で赤ちゃんを預けることがなくなってほしいと願います。
慈恵病院でSOS電話が始まってから10年が経ちますが、24時間のフリーダイヤルというかたちで妊娠に特化した相談を受けているのは、全国でも慈恵病院のSOS相談と田尻さんがかかわるスタディライフ熊本だけだと言います。田尻さんは、全国に相談窓口を普及させたいと取り組んでいます。

妊娠・出産での悩みを抱えている女性がたくさんいるのに、相談先が足りていないということはもっと社会に知ってもらいたい。学校では子どもたちに「いのちの授業」も行っています。「こうのとりのゆりかご」を通じて感じてきたことを、伝えていく責任が私にはある。私自身も、この問題のシンボルとして、活動を続けなくてはいけないと思っているんです。
「子どもが来てよかったね」と言える社会
田尻さんは、預けられた赤ちゃんたちがどうしているのかを、ずっと気にかけてきました。
まだ田尻さんが病院に勤めているとき、「こうのとりのゆりかご」に預けられた子どもが5歳になって、特別養子縁組の養親といっしょに訪ねてきたことがありました。「僕は慈恵病院で田尻さんから生まれたんだよ」と、その子が話すのを聞いて、思わず胸が詰まったそうです。
養親さんは惜しみない愛情でお子さんを育ててきたので、ためらうことなく事実を告知できたのだと思います。もちろん、こうした親子関係が築けている人ばかりではありません。中学生や高校生になってから出自の相談を受けることも多い。その受け止め方にも個人差があります。
2017年3月末時点で、ゆりかごに預けられた130人の赤ちゃんのうち、特別養子縁組をしたのは47人、里親のもとにいるのは26人、元の家庭に戻ったのは23人、そしていまも乳児院など施設にいるのは28人(※その他6人)と公表されています。
預けられた赤ちゃんが、その後を幸せに生きていくためにはどうしたらいいかを考えていかなくてはいけません。特別養子縁組などの家庭養育は、まだ一般的とは言えず、周囲の反応に悩んでいる人もいます。もっとオープンに「うちに来た子どもです」と言えて、「ああ、よかったね」とみんなが喜べるような環境になってほしい。血のつながりにこだわらず「家族」を築けるよう、社会の意識が変わっていくことも必要です。
お母さんも子どもも幸せに生きてほしい
いま67歳になる田尻さんは「まだ10年は活動を続けたい」と話します。それは、田尻さんが病院にいる間に預けられた赤ちゃんが、大きくなって訪ねてくるかもしれないから。

そのときは、しっかり受け止めてあげたい。そして、「命のバトンをつないでくれたお母さんがいるから、いまあなたがいるのよ」と伝えたいと思っているのです。
親しくなった相談者から、「熊本のお母さん」と呼ばれることもあるという田尻さん。それだけ親身に相談者に寄り添って、悲しみや喜びを共有してきたからなのだと思います。
「だって、お母さんにも子どもにも幸せに生きてほしいからね」と田尻さんはさらりと言いますが、つらく大変な相談をいくつも受け止めてきたはずです。
お母さんと子どもを孤立させず、妊娠・出産そして育児のさまざまなステージで多様な支援をしていくことで、つないでいける命があります。支援の選択肢がもっと増えていくことで、「こうのとりのゆりかご」が必要なくなる日がくるのかもしれません。
そのためには、血のつながりにこだわらない、さまざまな「かぞく」のあり方をあたたかく受け止める私たちの意識も必要でしょう。
田尻さんの笑顔の奥に、さまざまな親子を支えてきた力強さと覚悟を感じながら、わたしたちは熊本をあとにしました。

soarと認定NPO法人SOS子どもの村JAPANは、「もう一つの“かぞく”のかたち〜これからの社会的養育について考えよう」と題し、子どもたちにとってより望ましい「“かぞく”のあり方」とは何か、読者のみなさんと一緒に考えていく企画を展開しています。
本記事は、その企画のもとに取材・公開された連載記事です。
認定NPO法人 SOS子どもの村JAPAN ホームページ
SOS子どもの村JAPANの活動をサポートしたい方は、こちらからご寄付を受け付けています。
関連情報:
こうのとりのゆりかご(医療法人聖粒会 慈恵病院)ホームページ
一般社団法人 スタディライフ熊本 ホームページ
<1>親と暮らせないこの子たちに、安心できる家庭をつくってあげたい。「子どもの村福岡」で里親をする田原正則さんと子どもたちの日々
<2>キックオフイベントのレポート:地域の多様なひとが「かぞく」や子どもの育ちに関わる社会に。SOS子どもの村JAPAN、よしおかゆうみさんと考えるかぞくのあり方
<3>福岡は「里親」先進都市って知ってました?まちぐるみで子どもを育ててきた地域の軌跡
<4>どの子どもにも「生きていてくれて、ありがとう」と伝えたい。児童養護施設等から巣立つ子どもたちを支える「ゆずりは」高橋亜美さん
(写真/田島寛久)



